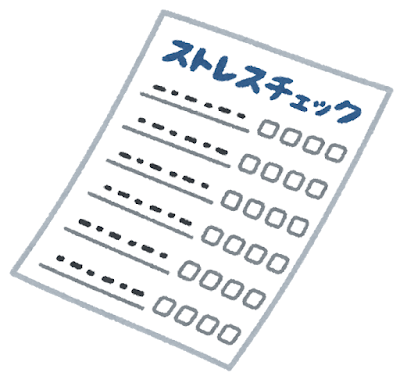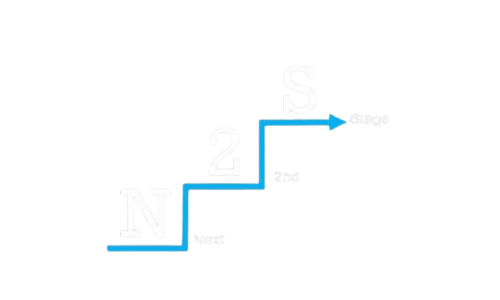NEWS
むくみ・冷え・気分の落ち込み…梅雨にありがちな不調の対策法
2025.6.15
こんにちは!門戸厄神駅前パーソナルトレーニングジム、N2Sパーソナルトレーナーの中阪です!
【不調を感じやすい6月。原因は“梅雨バテ”?】
雨が続く6月、「なんだか体が重い…」「朝からやる気が出ない」「手足が冷えてむくみやすい」——そんな不調を感じていませんか?
実はその原因、多くの人が見過ごしがちな“梅雨バテ”かもしれません。梅雨時期は、気圧の変化・高い湿度・日照不足によって、自律神経が乱れやすく、体も心も不調を感じやすくなるのです。
特にこんな人は要注意です:
• 朝起きるのがつらい
• 頭痛や肩こりが悪化する
• 食欲が落ちる or 甘いものがやめられない
• 気分が沈みやすい
• 何もしていないのに疲れやすい
このような状態が続くと、代謝の低下やホルモンバランスの乱れにつながり、**「むくみ」「冷え」「ストレス太り」**といったさらなる不調を引き起こすことも…。
でも、ご安心ください。
この記事では、そんな梅雨の不調に打ち勝つための「栄養」「運動」「生活習慣」の整え方を、運動初心者・子育て中のママ・働く女性・健康や美容に関心のある方にもわかりやすく解説していきます。
湿気に負けず、心も体も軽やかに過ごすための習慣を今日から始めてみませんか?
第1章:なぜ梅雨は体調を崩しやすいの?「だるさ」「不調」の正体
6月の梅雨シーズン。
湿気が多く、ジメジメとした空気に気分も沈みがち…。
「なんとなく体がだるい」「朝から頭が重い」「やる気が出ない」
そんな声をよく耳にしませんか?
実は、梅雨の不調には明確な原因があるのです。
この章では、6月に起こりやすい体調不良の原因について、科学的根拠とともにわかりやすく解説します。
⸻
■ 原因①:気圧変化による自律神経の乱れ
梅雨時期は低気圧と高気圧が交互に訪れるため、天候や気圧の変化が非常に大きくなります。この気圧の変化が、体の“自動調整システム”である自律神経に影響を与えます。
• 気圧が下がると副交感神経が優位になり、体はリラックスモードに
• 一方で、血管が拡張し血流が滞る → 【むくみ・頭痛・だるさ】の原因に
• 天候が不安定になると、交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかず、自律神経が乱れやすくなる
これが、梅雨にありがちな【気圧変化による頭痛】【倦怠感】【めまい】などの不調を引き起こします。
⸻
■ 原因②:高湿度と寒暖差がもたらす“冷え”と“むくみ”
梅雨のもう一つの特徴は、高湿度と気温差です。
• 湿度が高い → 発汗しにくく体に熱がこもる → 疲労感や眠気
• 外は蒸し暑くても、室内は冷房で冷えている → 下半身の冷えやむくみに
さらに、1日の寒暖差も大きくなるため、自律神経がフル稼働して疲弊。冷え性の方や女性は特に、手足の冷え・体の重だるさを感じやすくなります。
⸻
■ 原因③:日照不足による「気分の落ち込み」
梅雨は曇りや雨の日が多く、日照時間が圧倒的に不足します。
これにより、心の安定に必要な脳内物質「セロトニン」の分泌量が低下。
セロトニンが不足すると、以下のようなメンタル不調が現れます。
• 気分が落ち込む
• イライラしやすい
• 朝起きるのがつらい
• やる気が出ない
このような症状は「6月うつ」「気象病」とも呼ばれ、現代人に急増中です。特に女性や育児中のママは、ホルモンバランスの影響も加わり、梅雨のメンタル不調を強く感じやすい傾向があります。
⸻
■ 原因④:ライフスタイルの乱れが拍車をかける
加えて、梅雨特有の「外出しづらさ」や「気分の低下」が、生活リズムを乱す原因にも。
• 運動不足
• 寝つきの悪さ
• 栄養バランスの偏り
これらが自律神経やホルモンの働きをさらに乱し、不調を悪化させてしまいます。
つまり、「梅雨の体調不良」は単なる“気のせい”ではなく、環境的・生理的に起こりやすい仕組みがあるのです。
⸻
【まとめ】6月の体調不良は“複合的な要因”の結果
原因
引き起こす不調の例
気圧変化
頭痛・だるさ・めまい
高湿度・寒暖差
冷え・むくみ・疲労感
日照不足
気分の落ち込み・不安感
生活リズムの乱れ
自律神経の不調・免疫力低下
次章では、こうした不調の中でも特に多い「むくみ・冷え・気分の落ち込み」について、それぞれのメカニズムと具体的な対策を詳しく解説していきます。
第2章:むくみ・冷え・気分の落ち込み…梅雨に多い不調のメカニズムとは?
「朝起きても体が重い…」「なんだかずっと気分がスッキリしない」
そんな声が特に多くなるのが、6月の梅雨時期です。
この章では、梅雨に多くの人が感じる3つの代表的な不調──「むくみ」「冷え」「気分の落ち込み」──の具体的な原因と体のメカニズムについて解説します。
⸻
■ ①【むくみ】の原因:気圧×湿度×血行不良のトリプルパンチ
梅雨のむくみは、女性の大敵。とくに足・顔・手に症状が出やすく、夕方になると靴がきつくなる…なんて経験、ありませんか?
▼ 梅雨にむくみやすくなる理由
• 気圧の低下で血管が拡張 → 血流が滞りやすくなる
• 高湿度で汗が出にくい → 体内の水分が排出されず溜まる
• 運動不足・長時間の同じ姿勢でリンパの流れが悪化
これらの要因が組み合わさることで、体に余分な水分がたまり、むくみが慢性化してしまうのです。
⸻
■ ②【冷え】の原因:内外の温度差による体温調節の乱れ
「外は蒸し暑いのに、冷房の効いた室内では手足が冷たい…」
そんなアンバランスな環境も、冷えを加速させる大きな要因です。
▼ 梅雨の冷えのメカニズム
• 外気は湿気で熱がこもりやすく、汗もかきにくい → 体内に熱がこもる
• 室内はエアコンで冷えていて、急激な温度差で血管が収縮
• 結果として血流が悪化 → 末端(手・足)まで温かさが届かず「冷え」になる
女性は男性よりも筋肉量が少なく、もともと体温調節が苦手なため、より強く冷えを感じやすいのです。
⸻
■ ③【気分の落ち込み】の原因:セロトニン不足とストレス蓄積
「なんとなく憂うつ」「モヤモヤしてやる気が出ない」
これは**“気のせい”ではなく、脳の神経伝達物質の変化**によるものです。
▼ セロトニンが梅雨に減る理由
• 太陽光が少ない → セロトニンの分泌が減少
• セロトニンは“幸せホルモン”とも呼ばれ、感情や睡眠に関与する
• 減少により、イライラ・不安・不眠・うつっぽさを引き起こす
加えて、梅雨による活動量の低下・栄養の偏りも精神的不調を招きやすくなります。
現代人はストレス耐性が下がっているため、天候による小さな変化でも気分が落ち込みやすくなるのです。
⸻
■ まとめ:不調の根っこは「自律神経の乱れ」
不調
主な原因
影響する体のシステム
むくみ
気圧変化・湿度・運動不足
血流・リンパ循環
冷え
気温差・汗が出ない
体温調節機能
気分の落ち込み
日照不足・ストレス
自律神経・脳内ホルモン
このように、梅雨時期の代表的な不調はすべて「自律神経の乱れ」から始まるともいえます。
⸻
次章では、こうした不調に自分でできるケア方法として、「生活習慣」から自律神経を整える具体的な方法を紹介します。
第2章:むくみ・冷え・気分の落ち込み…梅雨に多い不調のメカニズムとは?
「朝起きても体が重い…」「なんだかずっと気分がスッキリしない」
そんな声が特に多くなるのが、6月の梅雨時期です。
この章では、梅雨に多くの人が感じる3つの代表的な不調──「むくみ」「冷え」「気分の落ち込み」──の具体的な原因と体のメカニズムについて解説します。
⸻
■ ①【むくみ】の原因:気圧×湿度×血行不良のトリプルパンチ
梅雨のむくみは、女性の大敵。とくに足・顔・手に症状が出やすく、夕方になると靴がきつくなる…なんて経験、ありませんか?
▼ 梅雨にむくみやすくなる理由
• 気圧の低下で血管が拡張 → 血流が滞りやすくなる
• 高湿度で汗が出にくい → 体内の水分が排出されず溜まる
• 運動不足・長時間の同じ姿勢でリンパの流れが悪化
これらの要因が組み合わさることで、体に余分な水分がたまり、むくみが慢性化してしまうのです。
⸻
■ ②【冷え】の原因:内外の温度差による体温調節の乱れ
「外は蒸し暑いのに、冷房の効いた室内では手足が冷たい…」
そんなアンバランスな環境も、冷えを加速させる大きな要因です。
▼ 梅雨の冷えのメカニズム
• 外気は湿気で熱がこもりやすく、汗もかきにくい → 体内に熱がこもる
• 室内はエアコンで冷えていて、急激な温度差で血管が収縮
• 結果として血流が悪化 → 末端(手・足)まで温かさが届かず「冷え」になる
女性は男性よりも筋肉量が少なく、もともと体温調節が苦手なため、より強く冷えを感じやすいのです。
⸻
■ ③【気分の落ち込み】の原因:セロトニン不足とストレス蓄積
「なんとなく憂うつ」「モヤモヤしてやる気が出ない」
これは**“気のせい”ではなく、脳の神経伝達物質の変化**によるものです。
▼ セロトニンが梅雨に減る理由
• 太陽光が少ない → セロトニンの分泌が減少
• セロトニンは“幸せホルモン”とも呼ばれ、感情や睡眠に関与する
• 減少により、イライラ・不安・不眠・うつっぽさを引き起こす
加えて、梅雨による活動量の低下・栄養の偏りも精神的不調を招きやすくなります。
現代人はストレス耐性が下がっているため、天候による小さな変化でも気分が落ち込みやすくなるのです。
⸻
■ まとめ:不調の根っこは「自律神経の乱れ」
不調
主な原因
影響する体のシステム
むくみ
気圧変化・湿度・運動不足
血流・リンパ循環
冷え
気温差・汗が出ない
体温調節機能
気分の落ち込み
日照不足・ストレス
自律神経・脳内ホルモン
このように、梅雨時期の代表的な不調はすべて「自律神経の乱れ」から始まるともいえます。
⸻
次章では、こうした不調に自分でできるケア方法として、「生活習慣」から自律神経を整える具体的な方法を紹介します。
第3章:生活習慣で整える!梅雨時期の自律神経ケア
梅雨の不調は「体質だから仕方ない」と思っていませんか?
実は、日々の生活習慣の見直しだけでも、自律神経のバランスは整えることが可能です。
この章では、「睡眠・食事・入浴・朝の過ごし方」など、すぐに実践できる自律神経ケアの生活習慣をご紹介します。
⸻
■ ① 朝の過ごし方で1日の自律神経が決まる!
自律神経は「朝の光」でスイッチが入ります。
梅雨は曇りや雨が多く、日照不足で交感神経のスタートが鈍くなりがち。
▼ 朝のおすすめ習慣
• 起きたらまずカーテンを開けて自然光を浴びる(5分でOK)
• 晴れの日はベランダや玄関先で深呼吸+軽いストレッチ
• 朝食にはたんぱく質・ビタミンB群・炭水化物をバランスよく摂取
これだけで、脳と体が「起きたよ!」とリズムを取り戻します。
⸻
■ ② 睡眠の質を高める「夜のルーティン」
自律神経の乱れで多い悩みの一つが「眠れない」「寝ても疲れが取れない」。
梅雨時期は湿度で寝苦しさも加わり、質の高い睡眠が取りにくくなる季節です。
▼ 自律神経を整える快眠習慣
• 寝る1時間前はスマホやPCを見ない(ブルーライトOFF)
• 湯船に38〜40度のぬるめのお湯で15分入浴(交感神経をリセット)
• アロマ(ラベンダーやカモミール)でリラックス
副交感神経を優位にすることで、眠りのスイッチが入りやすくなります。
⸻
■ ③ 食事で整える!「神経伝達物質」の材料を補給
気分の落ち込みや不調の原因であるセロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質は、食事から材料を摂ることが大切です。
▼ 自律神経を整える栄養素
栄養素
多く含む食材
働き
トリプトファン
大豆製品、卵、バナナ
セロトニンの材料
ビタミンB6
鶏むね肉、マグロ、にんにく
セロトニン生成をサポート
マグネシウム
納豆、海藻、アーモンド
神経の興奮を抑える
鉄分
赤身肉、ほうれん草
脳の酸素供給を助ける
「気分が落ちるから甘いものが食べたい…」と思ったときこそ、“心の栄養”を整える食品を意識的に摂るのがポイントです。
⸻
■ ④ 湿気と気圧に負けない体をつくる「日中の活動」
雨が続くと外出や運動が減りがちですが、自律神経のバランスを整えるには、日中の軽い活動が欠かせません。
▼ 室内でもできるおすすめ行動
• 朝と夕方に軽くラジオ体操やストレッチ
• エレベーターではなく階段を使う
• 雨が止んだタイミングで15分だけ散歩
運動により血行が改善され、交感神経・副交感神経の切り替えがスムーズになります。
⸻
■ まとめ:生活習慣のひと工夫で“だるさに負けない自分”に
「なんとなくだるい」「気分が上がらない」
そんな梅雨の悩みは、自律神経がSOSを出しているサイン。
ポイントは…
✅ 朝に光を浴びる
✅ 夜はぬるめのお風呂+スマホOFF
✅ 食事で神経の材料を補給
✅ 軽い運動で血流アップ
一つでも意識して取り入れることで、ジメジメした季節も、スッキリと健やかに過ごせる体づくりができます。
第4章:だるくて動けない…でもできる!梅雨の不調に効く「ゆる運動」のすすめ
◆ 梅雨の“動きたくない”は自然な反応だった!
6月になると、「体がだるくて動きたくない」「朝から眠い」「ずっと家にこもっていたい」──
こんな声をよく聞きます。でもそれ、決してあなたの「やる気がないせい」ではありません。
梅雨特有の「気圧の低下」「湿度の上昇」「日照時間の減少」などが重なり、自律神経のバランスが乱れることで“だるさ”を感じやすくなるのです。
つまり、「だるい」は体からのSOS。
実は“回復するために必要な動き”を、体が求めているサインでもあるのです。
⸻
◆ 梅雨のだるさに効く!運動がもたらす3つのメリット
運動と聞くと、「しんどい」「続かない」と思いがちですが、梅雨の不調にはむしろ“軽い運動”こそが効果的。
▶ 運動が体にもたらす変化はこの3つ!
効果
内容
✅ 血行促進
気圧変化による血流の停滞を改善し、むくみ・冷えを緩和
✅ 自律神経の調整
リズムある運動が交感神経と副交感神経を整え、不調に強くなる
✅ セロトニン分泌
幸せホルモンが分泌され、気分の落ち込みやイライラを和らげる
つまり、「動くことで、体が整い、心まで前向きになる」──
この時期こそ“やさしい運動”が、最高のセルフケアになるのです。
⸻
◆ 運動初心者さんでもOK!室内でできる簡単ゆる運動3選
【1】目覚めストレッチ(朝の3分)
ポイント:眠気・だるさを吹き飛ばす「交感神経スイッチ」
• 深呼吸×3回
• 両手を上に伸ばして大きく背伸び×3回
• 肩回し+首をゆっくり左右に倒す(各15秒)
→寝起きのぼんやりした頭がシャキッと整います。
⸻
【2】足踏み&手ふりエクササイズ(室内ウォーキング)
ポイント:太ももやふくらはぎのポンプ機能を活性化!
• その場で足踏み30秒×3セット
• 手も一緒に大きく振って全身運動に
→テレビを見ながらでもできる“ながら運動”でOK!
⸻
【3】お風呂あがりのゆるヨガ(入眠促進)
ポイント:副交感神経が優位になり、眠りが深くなる
• あぐらで座り、背中を丸める→反らす(ネコ&ウシポーズ)
• 両足を前に出して、ゆっくり前屈して深呼吸5回
→体の緊張がゆるみ、「ぐっすり眠れる体」に整います。
⸻
◆ 続けるための3つのコツ|がんばらない工夫が大事!
▷ コツ1:時間を決めて「生活に組み込む」
朝起きたら/お風呂の後/寝る前など、タイミングを固定するだけで続けやすくなります。
▷ コツ2:小さな“ごほうび”を用意
運動後にハーブティーや音楽タイムなど「心が喜ぶこと」をセットにすると習慣化しやすくなります。
▷ コツ3:記録をつけて“見える化”
アプリで記録したり、カレンダーにチェックを入れるだけで達成感が高まり、やる気が続きます。
⸻
◆ コラム:体が「止まりたい」ときこそ、“ちょっと動く”が正解!
梅雨の不調でやる気が出ないと、「今日は休もう」「何もしたくない」と感じるのは当然のこと。
でも、そんなときに“ほんの少しだけ体を動かす”ことが、実は自分を守る手段になります。
✔ 朝3分のストレッチ
✔ その場足踏み30秒
✔ 深呼吸しながら体を伸ばす
それだけでも、心も体も“スイッチが入る”のを実感できますよ。
⸻
◆ まとめ:軽い運動が、梅雨のだるさに効く一番の処方箋
6月のだるさや不調は、気合や根性では乗り越えにくいもの。でも、無理のない運動は、自然にあなたの心と体を整えてくれる最強の味方です。
• 毎日やらなくていい
• 完璧じゃなくていい
• 少しでも「動いた自分」を褒めてあげてください
心地よく体をゆるめる“梅雨のゆる運動”、今日からぜひ取り入れてみましょう!
第5章:湿気と冷えのダブルパンチ!むくみや冷えの原因と対策
◆ 梅雨は「むくみ」と「冷え」のダブルでつらい季節
梅雨の時期、こんな症状に悩んでいませんか?
• 足首やふくらはぎがパンパンに張ってつらい
• 手先が冷たくて、体がなかなか温まらない
• 朝起きたとき、顔がむくんで重だるい感じがする
これらの原因は、「湿気」「気温差」「運動不足」の三重苦による血行不良やリンパの流れの滞り。
放っておくと自律神経の乱れにもつながり、さらに不調の連鎖を引き起こすおそれがあります。
⸻
◆ むくみ&冷えが悪化する!梅雨特有の3つの要因
原因
説明
🌧 湿気
体内の余分な水分が排出されにくく、むくみやすくなる
🌡 気温差
室内外の寒暖差で体温調節が乱れ、冷えを感じやすい
🧘♀️ 運動不足
筋ポンプ機能が低下し、血液やリンパが滞る原因に
特に女性は「筋肉量が少ない」「ホルモンバランスの変化を受けやすい」ため、
梅雨の時期にむくみ・冷えの症状が強く出る傾向があります。
⸻
◆ 梅雨のむくみ・冷えを撃退!5つの実践的対策
【1】足首回し&つま先立ち運動(1日5分でOK)
• 椅子に座って片足ずつ足首をくるくる10回まわす
• つま先立ちを10回×3セット
→血流とリンパの流れが改善され、脚のむくみがスッキリ!
⸻
【2】ぬるめのお風呂で全身ぽかぽか(38〜40℃)
• 湯船に10〜15分浸かることで副交感神経が優位に
• むくみの原因である水分の滞りもリセット!
→バスソルトや炭酸入浴剤を使えば発汗&デトックス効果アップ。
⸻
【3】「カリウム」食材を取り入れる
カリウムには体内の余分な水分を排出する作用があります。
食材例
おすすめの摂り方
アボカド
サラダやトーストに
きゅうり
梅酢和えやピクルスで
バナナ
朝食やおやつ代わりに
【4】体を“温める食材”を積極的に
• 生姜、にんにく、ねぎ、根菜類
→冷えやむくみの原因である“内臓冷え”を防ぎます。
特に朝や夜に取り入れると、体の内側からポカポカに。
⸻
【5】締め付けすぎない服装を選ぶ
• ガードル・タイツなどの着圧が強すぎる服は避ける
• 冷房の冷え対策に、腹巻きやレッグウォーマーも◎
→血流の妨げを防ぎ、むくみを予防します。
⸻
◆ コラム:むくみや冷えは「代謝低下」のサインかも?
むくみや冷えは、体の巡りが悪くなっている証拠。
そのままにしておくと、「だるさ」「頭痛」「疲れやすさ」といった他の不調も誘発されます。
逆に言えば、
✅ むくみが減った
✅ 手足が温かくなった
✅ 朝の目覚めがスッキリ
これらの変化は、代謝が改善された“サイン”でもあるのです。
⸻
◆ まとめ:冷え&むくみケアで、梅雨の不調をリセット!
梅雨はただでさえ不快感が多い季節。
だからこそ、「体を温めて巡らせること」が何よりの不調対策になります。
• むくみ解消には“動かす・流す”が基本
• 冷え対策には“温める・整える”がカギ
• 小さなケアの積み重ねが、大きな不調を防いでくれる
今日からすぐに取り入れられる習慣ばかりなので、ぜひ実践してみてくださいね。
🧠第6章:心も沈みがち…梅雨の“気分の落ち込み”を防ぐメンタルケア
⸻
◆ 梅雨の空は、心にも影響する?
「なんだか最近、やる気が出ない」「イライラしたり、涙もろくなったり…」
6月に入ってから、そんな心の不調を感じていませんか?
実はそれ、**気のせいではなく“気象による脳へのストレス”**が関係しているんです。
⸻
◆ 気圧と日照不足が、脳と自律神経にストレスをかける
梅雨特有の【低気圧】【湿気】【日照不足】は、脳と神経にとって大きな負担。特に女性は、ホルモンバランスの変化も加わり、心の不調が出やすくなります。
梅雨の環境要因
心に与える影響
☁️ 日照不足
セロトニン(幸せホルモン)が減り、気分が沈む
🌧 気圧の低下
自律神経の交感神経が過剰に優位に→不安やイライラ
🛌 リズムの乱れ
睡眠・食事・運動が崩れやすく、心身のバランス悪化
◆ 脳と心を整える!“6月のメンタルケア習慣”5選
【1】朝の光を浴びる(曇りでも◎)
• 起きたらすぐカーテンを開けて、5〜15分ほど自然光を浴びましょう。
• 曇っていても「太陽の光」は脳に届き、セロトニンの分泌を促してくれます。
☀️ 朝の光=脳のスイッチをONにする「自然の処方箋」
⸻
【2】“ゆる運動”で心のもやもやを吹き飛ばす
• ストレッチ、ウォーキング、踏み台昇降、ヨガなど
• 運動によって**エンドルフィン(幸福感ホルモン)やドーパミン(やる気ホルモン)**が分泌されます。
🎧 好きな音楽をかけて動けば、気分はもっと前向きに!
⸻
【3】「気持ちの言語化」で感情を整える
• モヤモヤを紙に書き出す「ジャーナリング」
• 家族や友人に話すだけでもOK
→自分の気持ちを“言葉”にすることで、脳が冷静さを取り戻します。
💡「言葉にする」=ストレスの出口を作ってあげること
⸻
【4】食べ物から整える!“メンタルを支える栄養素”
栄養素
心への効果
含まれる食材例
トリプトファン
セロトニンの材料
バナナ、大豆製品、乳製品
ビタミンB6
神経の働きを助ける
鮭、鶏むね肉、にんにく
マグネシウム
ストレス軽減
ナッツ、玄米、海藻
🍽 甘いお菓子ではなく、「心に効く栄養」で満たしてあげましょう。
⸻
【5】“小さなご褒美”で脳にご機嫌スイッチを
• 香りのよい入浴剤でお風呂タイム
• 好きなハーブティーをいれる
• 1日5分のスマホOFFタイムで自分と向き合う
🌿「今ここ」に集中する時間は、脳に深い癒しをもたらします。
⸻
◆ 憂うつな気分は、“怠け”ではない
「気分が沈んで動けない…でもやらなきゃ」
そんな風に自分を責めてしまうあなたへ。
その気分の落ち込みは、“あなたが怠けている”のではなく、心と体が「少し疲れているよ」と教えてくれているサイン。
🌈 まずは「整えること」を大切にしましょう。
それが、前に進む力になります。
⸻
◆ この章のまとめ
• 梅雨時期は気圧・日照・リズムの乱れで心も疲れやすい
• セロトニン・エンドルフィン・ビタミンで“心の栄養”を補う
• 無理にポジティブにならなくていい。「整える習慣」が最強のメンタルケア!
第7章:腸を整えて気分もすっきり!“腸活”で自律神経をサポート
梅雨の時期になると、「なんとなく気分が沈む」「朝からだるい」「便秘気味でお腹がスッキリしない」――そんな体と心の不調を感じる人が増えます。
実は、これらの不調のカギを握っているのが“腸内環境”です。近年の研究では、腸と自律神経、そして心の状態には密接な関係があることがわかってきました。
つまり、腸を整えること(=腸活)によって、自律神経の乱れやメンタル不調も改善できる可能性があるのです。
この章では、梅雨に腸の調子が乱れやすい理由と、今すぐできる効果的な「腸活」習慣をわかりやすくご紹介します。
⸻
■ 梅雨と腸の関係:なぜこの時期に腸が乱れるの?
6月の梅雨時期は、気圧の変化や湿度の上昇、日照不足など、私たちの体にさまざまなストレスを与えます。とくに影響を受けやすいのが「自律神経」です。
腸の働きは自律神経によってコントロールされているため、ストレスや睡眠不足、運動不足などによって自律神経が乱れると、腸の働きも鈍くなります。
さらにこの時期は冷たい飲み物・アイスなどの摂取も増え、腸が冷えてしまい、腸内の血流が悪化。すると腸内環境はさらに悪化し、以下のような不調を引き起こします:
• 便秘・下痢の繰り返し
• ガスがたまりやすい・お腹が張る
• 肌荒れや吹き出物
• 情緒不安定・イライラしやすい
• やる気が出ない・気分の落ち込み
これらの症状に心当たりがある方は、腸からのSOS信号を見逃さないでください。
⸻
■ 腸は「第二の脳」? セロトニンと自律神経の深い関係
腸は、単に食べ物を消化・吸収する器官ではありません。
「腸は第二の脳」とも呼ばれるように、神経細胞が豊富で、自律神経と密接に連携しています。
実際、幸せホルモン「セロトニン」の約90%は腸で作られているという事実をご存じでしょうか?
つまり、腸内環境を整えることは、心の安定に直結します。
腸が元気=セロトニン分泌が活性化=自律神経が整う=気分が安定、という好循環が生まれるのです。
⸻
■ 今日からできる!腸活3つの習慣
① 発酵食品+食物繊維で善玉菌を育てよう
腸活の基本は「腸内細菌を育てる」こと。
まずは、**善玉菌を含む発酵食品(ヨーグルト、納豆、キムチ、味噌など)を1日1品取り入れてみましょう。
さらに、善玉菌のエサになる食物繊維(オートミール、ごぼう、わかめ、バナナなど)**を意識的に摂ると、腸内環境はスピーディーに整っていきます。
② 朝起きたら白湯を1杯。腸を「目覚め」させる
朝起きてすぐ、冷たい水ではなく**白湯(さゆ)**を1杯飲むだけで、腸の動きが活発になります。
白湯は腸をやさしく温め、自律神経の副交感神経を刺激し、リラックス効果も◎。
③ ストレス管理と睡眠の質にも注目を
いくら食生活を整えても、ストレスが多いと腸の働きは乱れます。
簡単なヨガ、ストレッチ、深呼吸、お風呂にゆっくり浸かる時間をつくって、副交感神経を優位にしましょう。
また、睡眠不足や寝る前のスマホ習慣も腸にはNG。夜は照明を暗めにして、ぐっすり眠る環境づくりを。
⸻
■ 腸から梅雨バテ解消!「心と体に効く腸活」は今がはじめ時
気圧や気温、湿度の変化が激しい6月は、自律神経も腸も揺らぎやすい時期です。
でも、だからこそ“腸活”を習慣にすることで、心も体も整えるチャンスになります。
しかも腸活は、難しいことはありません。
・朝の白湯
・味噌汁や納豆など日本の伝統的な食材をとる
・寝る前に5分間のリラックスタイムをつくる
といった、小さなことの積み重ねが、やがて大きな変化になります。
ぜひ今日から「腸にやさしい生活」を意識して、自律神経も整えていきましょう。
⸻
次の章では、冷えやむくみを改善しながら気分もすっきりする「簡単ストレッチ&筋トレ習慣」をご紹介します。運動初心者でもできる内容なので、どうぞお楽しみに!
第8章:ぐっすり眠って回復力アップ!梅雨時の快眠法
梅雨の時期は、湿気や気温の変化、日照時間の減少により、睡眠の質が落ちやすくなります。ぐっすり眠れないと、体はもちろん、心にも疲れが蓄積し、自律神経のバランスも乱れがちに…。この章では、梅雨の不調を防ぐための「快眠のコツ」を詳しくご紹介します。
⸻
1. 梅雨に眠れないのはなぜ?睡眠の質が下がる3つの原因
① 湿度の高さで寝苦しくなる
梅雨の時期は湿度が高く、皮膚からの汗の蒸発が妨げられます。このため、寝ている間も体温調節がうまくいかず、寝苦しさを感じやすくなります。
② 自律神経の乱れで入眠しにくい
気圧の変化や日照時間の減少により、自律神経が乱れやすくなります。副交感神経がうまく働かないと、リラックスできず「寝つきが悪い」「眠りが浅い」などの問題が起こります。
③ 憂うつな気分が睡眠に影響
雨の日が続くと気分が落ち込み、交感神経が過剰に優位になることも。精神的ストレスが重なると、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が減り、熟睡しづらくなります。
⸻
2. 快眠のために意識したい生活習慣
◎ 就寝1時間前は「ゆるやかな時間」に
寝る直前までスマホを見たり、仕事のメールをチェックしたりすると、脳が興奮状態に。就寝の1時間前は「間接照明を使う」「湯船につかる」「ストレッチをする」など、緊張をほどくルーティンをつくりましょう。
◎ 湿度管理で寝室環境を整える
理想的な寝室の湿度は40~60%。除湿器やエアコンのドライ機能、除湿シートなどを使い、カビや不快な蒸し暑さを防ぎます。
◎ 光の力を活用しよう
日中はカーテンを開けて自然光を浴び、体内時計を整えることが大切。朝に明るい光を浴びることで、メラトニンの分泌が夜に促され、眠りの質が向上します。
⸻
3. 食事で快眠をサポート!眠りを促す栄養素とは?
◆ トリプトファン(セロトニンの材料)
バナナ、乳製品、大豆製品などに含まれ、睡眠ホルモン「メラトニン」の原料となります。
◆ マグネシウム
自律神経を整えるミネラルで、アーモンド、海藻、玄米などに含まれます。
◆ ビタミンB6
トリプトファンの働きを助ける栄養素。まぐろ、鮭、バナナなどがおすすめです。
⸻
4. 梅雨の夜を快眠タイムに変える!おすすめ習慣まとめ
おすすめ習慣
ポイント
湯船に浸かる
寝る1時間前に38~40℃のお風呂で副交感神経を優位に
寝室の湿度を整える
除湿機やエアコンのドライ機能を活用
就寝前のブルーライトを避ける
スマホやPCは早めにオフにして、リラックスモードへ
リラックス音楽を活用
α波を促すヒーリング音楽なども効果的
アロマを取り入れる
ラベンダーやカモミールの香りは自律神経のバランスを整える効果が期待できます
5. まとめ:眠りを味方に、梅雨の不調をリセットしよう
睡眠は、心と体のリセットタイム。梅雨時のだるさ、イライラ、気分の落ち込みを和らげるためにも、「快眠」は欠かせない要素です。生活習慣・寝室環境・食事を整えることで、自律神経が整い、6月を健やかに過ごせるようになります。
次章では、雨の日でも気軽にできる運動習慣についてご紹介します!
第9章:梅雨にぴったりの運動習慣!雨の日でもできる簡単エクササイズ
梅雨になると、「外に出たくない」「ジムに行くのが億劫」「つい家でゴロゴロしてしまう…」と、運動不足になりがちです。しかし、運動は自律神経を整え、心身の健康をサポートする重要な習慣。特に梅雨のような不安定な季節こそ、適度な運動が心と体のバランスを保つカギになります。
ここでは、雨の日でも無理なくできる簡単エクササイズや運動習慣をご紹介します。
⸻
1. なぜ梅雨に運動が必要なの?
• 気圧や湿度の変化により、自律神経が乱れやすくなる
• 雨で活動量が減ると、血行不良・代謝低下・むくみの原因に
• 気分の落ち込みやストレスを解消するには、運動が効果的
→ 特に「軽く汗をかく」「体をほぐす」ような運動が、ストレスホルモンを抑え、セロトニンなどの“幸せホルモン”を促進します。
⸻
2. 家でできる!おすすめ簡単エクササイズ3選
【① スクワット(下半身強化&代謝アップ)】
• やり方:肩幅に足を開き、ゆっくり腰を落とす → 10〜15回×2セット
• 効果:下半身の筋力アップ/血流促進/冷え・むくみの解消
【② ストレッチヨガ(心身のリラックスに)】
• やり方:深呼吸をしながら「ねじりのポーズ」「猫のポーズ」などをゆったりと行う
• 効果:副交感神経が優位になり、リラックス効果&睡眠改善
【③ 腸活マッサージ&ドローイン】
• やり方:仰向けに寝て、お腹を時計回りにやさしくマッサージ。その後、鼻から息を吸ってお腹をへこませて10秒キープ。
• 効果:腸の働きが活発に。便秘・冷え性・イライラの改善に。
⸻
3. 気軽に取り入れよう!1日10分でOKの運動習慣
運動のタイミング
内容例
期待できる効果
朝の目覚めに
ラジオ体操・太陽礼拝
交感神経を活性化/1日の代謝UP
昼のスキマ時間に
椅子スクワット・肩回し
筋肉のこわばり解消/血流促進
夜のリラックスに
深呼吸ストレッチ・ヨガ
副交感神経を優位に/快眠サポート
ポイントは「無理なく・こまめに・毎日続けること」。激しい運動ではなく、気分が晴れるような動きから始めてみましょう。
⸻
4. モチベーションを保つ工夫
• お気に入りの音楽を流しながら動く
• スマホアプリやSNSで記録を残す
• 家族や子どもと一緒に楽しむ
• 自分に「よくできた!」と声をかけてあげる
運動は“やらなきゃ”と思うとハードルが上がってしまいます。生活の中に自然に組み込む“習慣化”が、継続のコツです。
⸻
5. まとめ:雨の日こそ「おうち運動」で心と体を整えよう
梅雨の運動不足は、気づかぬうちに体調不良や気分の落ち込みにつながります。でも、たった10分の軽い運動を続けるだけで、自律神経は整い、体も心もスッキリ快調に。外に出られない日は「チャンスの日」と考えて、自分のペースで体を動かしていきましょう。
次章では、梅雨の時期にありがちな“むくみ・冷え・頭痛”の具体的な対策法について解説します!
第10章:つらいむくみ・冷え・頭痛に!梅雨特有の不調への具体策
梅雨の季節になると、「なんとなく体が重い」「足がパンパンにむくむ」「頭がズキズキして集中できない」といった不調に悩む方が増えます。これらの症状はすべて、気圧・気温・湿度の変化によって乱れる自律神経の影響が大きく関係しています。
この章では、特に多くの女性が悩まされやすい「むくみ・冷え・頭痛」に焦点をあて、その対策方法を詳しくご紹介します。
⸻
1. 梅雨の「むくみ」の原因と対策
▶︎ 原因
• 湿度が高く、汗が蒸発しにくくなるため水分が体にたまりやすい
• 運動不足で血行やリンパの流れが悪くなる
• 塩分や糖分の多い食事で体内の水分バランスが崩れる
▶︎ 対策
• カリウムを含む食材を積極的に
→ きゅうり、アボカド、バナナ、スイカなど
• 下半身を動かすストレッチやウォーキング
→ 第二の心臓といわれるふくらはぎの筋肉を活性化
• 着圧ソックスや足湯でケア
→ 血流とリンパの循環を促進
⸻
2. 「冷え」による不調とその防止法
▶︎ 原因
• 外気と冷房の温度差で自律神経が乱れ、末端の血流が低下
• 濡れた服や足元の冷えがそのまま残り、体温調整がうまくいかない
▶︎ 対策
• 首・手首・足首を冷やさない服装を意識
→ 「3つの首」を温めると全身の血流がよくなる
• 温かい飲み物や味噌汁を朝・夜に取り入れる
→ 胃腸から温めて内側から冷えを防止
• 軽い筋トレや体幹トレーニング
→ 筋肉量UPで「燃えるカラダ」へ
⸻
3. 「頭痛」に悩む人へ、気圧対策の新習慣
▶︎ 原因
• 気圧の低下により血管が拡張し、神経を刺激
• 自律神経が乱れ、血管の収縮と拡張が交互に起きる
▶︎ 対策
• 朝の深呼吸+カフェインを適量摂取
→ 血管を収縮させ、ズキズキを予防
• こめかみや首筋を温める or 冷やす(症状に応じて)
→ 拡張型の偏頭痛:冷やす
→ 緊張型の頭痛:温める
• 天気痛対策アプリや日記で“変化”を記録
→ 自分の不調の傾向を知ると、早めの対策ができるようになる
⸻
4. “症状別おすすめ習慣”まとめ
不調の種類
日常でできる対策
おすすめ食品
むくみ
足のマッサージ、カリウム摂取、着圧ソックス
きゅうり、アボカド、海藻類
冷え
首元を温める、体幹トレーニング、湯船に浸かる
生姜、味噌汁、根菜、紅茶
頭痛
深呼吸、カフェインの活用、ツボ押し
緑茶、コーヒー、ナッツ類
5. 梅雨の不調は“気づいてケア”すればコントロールできる
むくみ・冷え・頭痛など、梅雨にありがちな体の不調は、我慢して放っておくとどんどん悪化してしまうこともあります。しかし、「なぜ起きるのか?」を知り、日常生活にちょっとした工夫を取り入れるだけで、快適に乗り切ることができます。
「今の自分、ちょっと不調かも…」と思ったら、無理をせず、自分の体と心にやさしく寄り添う時間を持ってあげましょう。
第11章:心も不安定になりがちな梅雨…メンタルケアのための習慣と考え方
梅雨時期は体だけでなく、心もなんとなく重く、沈みがちになる時期。日照時間が短く、気圧も変化しやすい環境が続くことで、自律神経が乱れ、気分の落ち込みやイライラ、不安感といった精神的な不調を引き起こしやすくなります。
とくに感受性の高い方や、ストレスを感じやすい女性や子育て中のお母さんには、メンタル面のケアが欠かせません。
この章では、心のバランスを整えるための生活習慣・思考のヒント・セルフケア方法を丁寧に解説していきます。
⸻
1. 梅雨がメンタルに与える影響とは?
▶︎ 気分の浮き沈みが起こる主な理由
• 日照時間の減少 → セロトニンの分泌低下
→ セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、感情の安定に重要な神経伝達物質
• 低気圧で自律神経が乱れる → 睡眠や集中力が低下
• 湿気・寒暖差 → 身体がだるくなり、心にも影響が出る
⸻
2. “朝のルーティン”でセロトニンを活性化!
朝の過ごし方を少し意識するだけで、1日のメンタルが安定しやすくなります。
▶︎ 心を整える朝の習慣3つ
1. 朝起きたらカーテンを開けて自然光を浴びる(曇りでもOK)
→ 体内時計をリセットし、セロトニンが分泌される
2. 軽くストレッチ or 5分の散歩
→ 運動もセロトニンの分泌を助ける
3. 深呼吸 or 呼吸瞑想(マインドフルネス)
→ 自律神経が整い、不安や焦りを静めやすくなる
⸻
3. 食事で「心の栄養補給」をしよう
▶︎ メンタルにやさしい栄養素と食材
栄養素
作用
含まれる食品
トリプトファン
セロトニンの材料
納豆、豆腐、チーズ、バナナ、卵
ビタミンB群
神経の働きを整える
玄米、豚肉、卵、緑黄色野菜
マグネシウム
自律神経やストレス調整に効果
アーモンド、海藻類、枝豆
梅雨の時期こそ、「食べること=心の安定剤」だと考え、無理なダイエットよりも栄養バランスの取れた食生活を意識することが大切です。
⸻
4. 考え方のクセを整える“コーピング”という選択
梅雨時期の不安や気分の落ち込みは、一時的な天候や体調の変化によるものであることがほとんどです。
▶︎ 「今の私は天気の影響を受けているだけ」と言葉にする
→ 状況を客観視することで、気分に振り回されにくくなります。
▶︎ 書き出してみる(ジャーナリング)
→ 自分の気持ちや思考をノートに書くだけで、不安や怒りが整理され、心が落ち着きます。
▶︎ 小さな「ご褒美タイム」を作る
→ 湯船にゆっくり浸かる、アロマを炊く、美味しいおやつを食べるなど、自分を労わる時間を持ちましょう。
⸻
5. “がんばらない”が梅雨メンタルには効果的
梅雨の時期は、普段のように元気に過ごせない日があって当たり前。そんなときは「今日だけはゆるくいこう」「80%の力でOK」と、自分にやさしい許可を出してあげましょう。
**「完璧じゃなくていい」「何もしない日も必要」**という考え方を取り入れることが、実は最も大きなメンタルケアにつながります。
第12章:子育て中・仕事中でもできる!“ながらセルフケア”のすすめ
梅雨の時期、心や体が重く感じるのは多くの人に共通する悩みです。しかし、「ケアしたくても時間がない」「子どもがいるからゆっくりできない」「仕事が忙しくて何もできない」と感じている方も多いのではないでしょうか?
そんな方におすすめなのが、“ながらセルフケア”。
特別な時間を設けなくても、日常の中でちょっと意識するだけでできるセルフケア方法を紹介します。これなら、子育て中のお母さんや多忙なビジネスパーソンでも無理なく実践できますよ。
⸻
1. 家事や育児の合間にできる簡単リセット法
▶︎ 洗い物しながら“つま先立ちストレッチ”
• 洗い物や料理中にかかとを上下に動かすだけで、ふくらはぎの筋ポンプが刺激されて血流がアップ!
• むくみや冷えの予防にも◎
▶︎ 掃除機をかけながら深呼吸
• 掃除機をかけるリズムに合わせて、鼻から吸って、口からゆっくり吐く
• 呼吸に意識を向けるだけで、自律神経が整いやすくなります
⸻
2. デスクワーク中の“こっそりリフレッシュ術”
▶︎ パソコン作業中の肩まわし
• 両肩を前後にゆっくり10回まわすだけ
• 肩こり予防と自律神経の緊張緩和に効果的
▶︎ 1時間に1回、1分間の立ち上がり&伸び
• たった1分で全身の血流が促進され、頭もスッキリ!
▶︎ 足元にペットボトルを置いてコロコロ
• 冷え対策&足裏刺激でリラックス効果UP
⸻
3. お風呂&トイレタイムも「自分時間」に変える
▶︎ お風呂で“香りと温度”のダブルリラックス
• 好きなアロマ(ラベンダーや柑橘系)を湯船に数滴垂らすだけで、副交感神経が優位になり深いリラックス
• 38〜40℃のぬるめの湯で15分程度が目安
▶︎ トイレで1分、目を閉じて“思考を手放す”
• 子どもから一瞬離れられる貴重なタイミング
• スマホではなく、自分の心と向き合う1分間にするだけで心の回復が早まります
⸻
4. 忙しい人ほど意識したい「ながら食事」の改善
▶︎ 食事中だけは“スマホを置く”習慣
• 情報をシャットアウトし、「食べること」に集中するだけで副交感神経が優位に
▶︎ 一口ごとに噛む回数を増やす
• よく噛むことで満腹感も得られ、消化促進やセロトニン分泌も期待できます
⸻
5. 子どもと一緒に「遊びながら運動」もおすすめ!
▶︎ おうちでできる“親子ヨガ”や“リズム体操”
• 小さな子どもと一緒に体を動かすことで、ストレス発散&運動不足解消
• 親子のスキンシップにもつながるので、心の安定にも◎
⸻
まとめ:ながらケアは、継続がカギ!
“ながらセルフケア”は、毎日の中に自然に取り入れられるからこそ、無理なく続けられるのが最大のメリット。
「少しずつでも、自分の心と体を大切にする時間をもつ」
それが、梅雨の不調を乗り越える大きな力になります。
第13章:まとめ|梅雨を乗り切る健康習慣を今日から始めよう
長く続く雨、低気圧、湿度の高さ…。
6月の梅雨は、心身のバランスが崩れやすい季節です。
特に「むくみ・冷え・気分の落ち込み」といった不調は、自律神経や血行、腸内環境など、複数の要因が複雑に絡み合って生じます。だからこそ、一つの方法だけに頼るのではなく、日々の生活習慣全体を見直していくことが大切です。
⸻
本記事で紹介した梅雨の不調対策まとめ
💡 食事で整える
• ビタミンB群、マグネシウム、たんぱく質、発酵食品などで自律神経や腸内環境をサポート
💡 運動でめぐりを改善
• 無理なくできる軽い運動やストレッチ、ウォーキングなどで血行を促進し、ホルモンバランスも整える
💡 生活リズムと睡眠の質を見直す
• 起床・就寝時間を一定に保ち、朝日を浴びる習慣を取り入れることで体内時計が整う
💡 心のセルフケアも忘れずに
• 呼吸法、マインドフルネス、アロマなど、自分に合ったリラックス法を見つける
💡 ながらセルフケアを活用
• 忙しい中でもできる“ながら”ケア(家事中、仕事中、入浴中など)を生活の一部に取り入れる
⸻
「ちょっとずつ」が一番続くコツ!
完璧を目指さなくてもOKです。
たとえば、「朝起きたら白湯を飲む」「エレベーターではなく階段を使う」など、小さな一歩を積み重ねることが、6月の不調対策において何よりも効果的です。
そして何より、“自分の体の声に耳を傾けること”が、最も大切なセルフケアの第一歩。
⸻
最後に:梅雨は「自分を見つめ直すチャンス」
6月は気分が落ち込みやすいからこそ、
「少し立ち止まって、自分をケアする」ことに意識を向けてみましょう。
この記事が、皆さんの健康的な毎日をサポートするきっかけになれば幸いです。
次回は「夏に向けて体調を整える方法」や「紫外線対策」などのテーマもお届け予定ですので、ぜひご期待ください!
番外編:学生さんも要注意!梅雨の体調管理で集中力アップ
梅雨の時期は、実は学生さんにとっても体調やメンタルが不安定になりやすい季節です。
テスト勉強、部活動、進路へのプレッシャー…ストレスや疲れがたまりがちなこの時期、ちょっとした習慣の工夫で、ぐっと集中力も上がります!
⸻
1. 雨の日のだるさ…原因は「自律神経の乱れ」
「朝起きられない」「授業に集中できない」「イライラする」…
その原因は、梅雨の気圧の変化や日照不足による自律神経の乱れかもしれません。
✅ スマホの見すぎで寝不足
✅ 朝食を抜く
✅ 運動不足
こうした生活は、自律神経のバランスを乱し、心や体の不調を引き起こす原因になります。
⸻
2. 学生でもできる!梅雨を元気に乗り切る3つの習慣
(1)朝食は「脳のエネルギー源」
朝ごはんを抜くと、集中力が激減!
ごはん+たまご+味噌汁など、シンプルでもOK。
バナナやヨーグルトなどの発酵食品もおすすめ!
(2)5分だけでも体を動かす
運動は脳を活性化させ、気持ちもリフレッシュできます。
朝にストレッチ、通学時は一駅歩く、階段を使うだけでも効果的。
(3)寝る前スマホをやめて「睡眠の質」UP
夜遅くまでSNSや動画を見ていませんか?
画面のブルーライトは睡眠の質を下げます。
寝る30分前はスマホをやめて、ゆったりした音楽や読書で気持ちを落ち着けましょう。
⸻
3. 心が落ち込んだときは…
「なんだか疲れる」「やる気が出ない」そんな時は、無理をせずに心のSOSに気づくことも大切。
• 先生や家族に相談する
• カフェで一息つく
• 音楽や散歩で気分転換
体と心はつながっています。無理せず、自分を大事にしていきましょう。
⸻
まとめ:今からできることで、6月を乗り切ろう!
梅雨の不調は、ちょっとした習慣の見直しで改善できます。
勉強も部活も、健康な心と体があってこそ。
学生のみなさんも、自分自身の体調と心の声に耳を傾けながら、毎日を前向きに過ごしていきましょう!