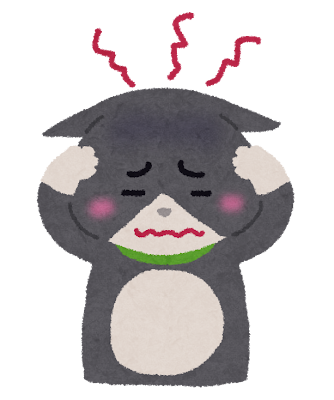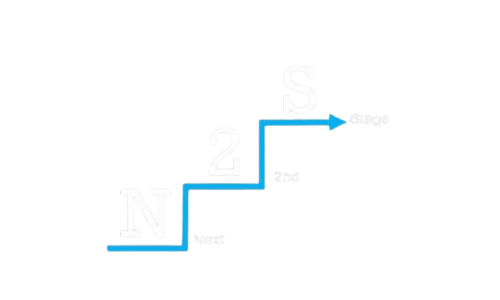NEWS
気圧の変化でズキズキ頭痛…その原因と対策法|梅雨や台風シーズンも快適に過ごすコツ
2025.6.23
こんにちは!門戸厄神駅前パーソナルトレーニングジム、N2Sパーソナルトレーナーの中阪です!
「最近、雨が降りそうな日に決まって頭がズキズキする」「台風が近づくと気分も体調もどんよりする」——そんなお悩み、ありませんか?
特に6月の梅雨の時期は、天候が安定せず、気圧が乱高下しやすくなります。この気圧の変化が原因となって引き起こされる体調不良は、「気象病(天気痛)」として注目されており、偏頭痛やめまい、だるさ、気分の落ち込みなど、実にさまざまな不調の引き金になります。
実はこの症状、単なる気のせいではなく、自律神経の乱れや血流の変化と密接な関係があるのです。そして、対策は“あります”。
本記事では、
• 気圧の変化と偏頭痛のメカニズム
• 生活習慣や運動、栄養で整える改善法
• 特に女性に多い自律神経の不調へのサポート法
などを、わかりやすく・実践しやすく解説。社会人女性、子育て中のママ、美容や健康に関心の高い方、運動初心者にもおすすめの内容です。
梅雨を快適に過ごしたい方必見! 今からできるセルフケアで、“気圧に振り回されない私”を一緒に目指しましょう。
⸻
🌧 第1章:はじめに|気圧と偏頭痛は無関係じゃない!
「天気が悪くなると、なぜか頭が痛くなる……」
「雨の日は、体が重くてやる気が出ない……」
そんな不調を感じたことはありませんか? その原因、実は“気圧”かもしれません。
気圧の変化が引き起こす体調不良は、「気象病」や「天気痛」として知られ、最近ではテレビや雑誌などでもたびたび取り上げられるようになってきました。
▶ 偏頭痛と気圧変化の関係性
特に多くの人が感じやすいのが「気圧性頭痛(気象性偏頭痛)」。これは、気圧が低下したタイミングで血管が拡張し、脳の神経を刺激することで起こる頭痛です。
また、気圧の変動によって自律神経が乱れると、身体のさまざまな部位に影響が出てきます。例えば、
• 血流が悪くなって酸素が不足し、頭痛が起こる
• セロトニン(精神を安定させる神経伝達物質)の分泌が乱れて、気分が落ち込む
• 内耳の気圧センサーが過敏になり、めまいやふらつきが出る
といった症状がよく見られます。
▶ 特に女性は要注意!
女性はホルモンバランスの影響を受けやすく、さらに気圧の変化による自律神経の不調が重なりやすいため、偏頭痛や倦怠感などが強く出やすい傾向にあります。
さらに、子育てや仕事、家事などのストレスが蓄積されていると、体はより敏感に気圧変化をキャッチしてしまいます。
第2章:なぜ気圧で体調が崩れるの?そのメカニズムを解説
雨が降り出す前や台風の接近時、なんとなく体が重く感じたり、頭が痛くなったりすることはありませんか? それは、気圧の変化がもたらす**「見えないストレス」**が体に影響を与えている証拠です。
この章では、「なぜ気圧の変化が体調不良を引き起こすのか?」そのメカニズムを分かりやすく解説します。
⸻
▶ 気圧の低下で血管が広がる
天気が崩れるとき、気圧(=空気の重さ)は下がります。これにより体内の血管は、外からの圧力が弱くなるため拡張しやすくなります。
特に脳内の血管が広がると、その周囲にある神経を刺激し、ズキズキとした偏頭痛を引き起こすのです。
⸻
▶ 自律神経がバランスを崩す
気圧の変化は、私たちの体の“センサー”である**内耳(ないじ)**や、**視床下部(ししょうかぶ/自律神経の司令塔)**に刺激を与えます。
これにより、交感神経と副交感神経のバランスが乱れ、以下のような不調が現れます。
• 頭痛・肩こり
• めまい・ふらつき
• 胃腸の不調(便秘・下痢・食欲不振)
• 冷え・むくみ
• 気分の落ち込み・不安感
とくに、ストレスを抱えている人・女性・気象変化に敏感な体質の人は、自律神経の調整機能が過剰に反応してしまい、不調が顕著になりやすいのです。
⸻
▶ 気圧変化は「見えないストレス」
私たちは天気の変化に「気を張る」ことは少なく、つい無意識のうちに過ごしてしまいます。しかし実際には、天候=自然の変化が自律神経にとってのストレスとなっているのです。
だからこそ、「気のせいかな?」で済まさずに、**“気圧の乱れ=体調も揺らぎやすいサイン”**と認識することが、セルフケアの第一歩になります。
⸻
▶ 女性はより影響を受けやすい理由
女性はホルモンのリズム(月経・排卵・更年期など)が自律神経に影響するため、気圧の変化+ホルモン変動のWパンチで体調不良が出やすくなります。
特に生理前後や排卵期は自律神経が敏感になっており、気圧変化による症状が強く出るケースも多いのです。
⸻
次章では、こうした気圧性の不調を**「薬に頼らず整える」方法**として、まず「生活習慣」からできるケア方法をご紹介します。
第3章:生活習慣で整える!梅雨時期の自律神経ケア
気圧の変化により自律神経が乱れると、頭痛・倦怠感・イライラなど、さまざまな不調が現れます。特に6月の梅雨時期は、湿度や気温の上下動も重なり、体が適応しきれずに“なんとなく不調”が続いてしまうことも…。
ですが、毎日の生活習慣を少し工夫するだけで、自律神経の乱れをやわらげ、気圧性不調に負けない体をつくることができます。
この章では、梅雨にこそ見直したい生活習慣のコツをご紹介します。
⸻
▶ 朝の光を浴びて「体内時計」を整える
人の体は、「太陽の光を浴びること」でリズムが整うようにできています。朝起きたら、まずカーテンを開けて日光を浴びることを習慣にしましょう。
朝日を浴びるメリット:
• 自律神経の切り替えがスムーズになる
• セロトニン(幸せホルモン)が分泌され、気分が安定する
• 睡眠ホルモン・メラトニンのリズムが整う
曇りや雨でも、外の光には十分な「照度(ルクス)」があります。雨の日でも5〜10分、ベランダや窓辺で外の光を浴びるだけで効果が期待できます。
⸻
▶ 湯船につかって“副交感神経”を優位に
シャワーだけで済ませず、ぬるめ(38~40℃)の湯船に10〜15分つかることをおすすめします。湯船に浸かると、副交感神経が優位になり、全身がリラックス状態に。
特に梅雨時期は冷房や湿気の影響で体が冷えがちです。お風呂でしっかり体を温めることは、血流改善・冷え対策・むくみ予防にもつながります。
入浴後はストレッチや深呼吸を加えると、さらにリラックス効果が高まります。
⸻
▶ 質の良い睡眠で「自律神経の修復」を促す
睡眠中は、自律神経のバランスが整う大切な時間です。以下のような工夫で、眠りの質を高めましょう。
• 寝る2時間前までに入浴を済ませておく
• 寝室は暗く・静かに・涼しく保つ(エアコンは28℃前後)
• スマホやPCは寝る1時間前までにオフに
• カフェインは夕方以降控える
日中のストレスや気圧による緊張を和らげ、深い眠りを促すことが、不調改善の鍵になります。
⸻
▶ 食事のタイミングも自律神経に影響
梅雨時は食欲が落ちる人も多いですが、朝・昼・夜を規則正しく摂ることが、体内リズムの安定に役立ちます。
特に朝食は「交感神経のスイッチ」を入れる大切な役割を持っています。温かいスープやお味噌汁を取り入れて、胃腸をやさしく目覚めさせましょう。
⸻
▶ 自律神経を整える生活習慣まとめ
習慣
ポイント
朝日を浴びる
セロトニン分泌・体内時計のリセット
湯船につかる
副交感神経が優位に・リラックス促進
良質な睡眠
自律神経の回復時間を確保
規則正しい食事
交感神経の安定、体温・血糖リズム維持
気圧の変化は防げなくても、「乱されにくい体」をつくることは可能です。
次章では、自律神経のバランスをさらにサポートしてくれる「栄養と食べ物」について、具体的な選び方とおすすめ食材を紹介します。
第4章:なぜ梅雨は「気分が落ち込みやすい」のか?心と気圧の関係
6月の梅雨時期になると、「やる気が出ない」「気持ちが沈む」「何をするにも億劫」──そんな“こころの不調”を感じる方が少なくありません。
この章では、気圧の変化が私たちの心に与える影響と、メンタルバランスを保つための具体策を解説します。
⸻
◆ 気圧が心に与える影響とは?──天気が悪いだけで落ち込むのはなぜ?
梅雨のように雨が続く時期は、気圧が低い状態が長く続きます。この「低気圧」は、私たちの体や心に以下のような影響を与えることが知られています。
● 自律神経が乱れる
気圧の変化により、交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、心身ともに緊張や不安を感じやすくなります。
● セロトニン分泌が減る
日照時間が減ることで、**幸せホルモン“セロトニン”**の分泌量が低下。気分の落ち込みやイライラの原因に。
● 酸素の取り込みが減少
低気圧下では空気が薄くなり、体内の酸素量もわずかに減少。脳の働きが鈍くなり、集中力や意欲も下がります。
⸻
◆ 梅雨うつ・気象病チェックリスト
• 雨の日や曇りの日に気分が沈みがち
• 朝から疲れが取れない
• 眠っても眠ってもだるさが抜けない
• 何もしていないのにイライラ・不安になる
• 頭痛や肩こりが悪化する
ひとつでも当てはまるなら、「梅雨の気象ストレス」が影響している可能性大です。
⸻
◆ 気分の落ち込みを防ぐ3つのポイント
①「朝の光」を味方にする
梅雨時期でも、朝にカーテンを開けて自然光を浴びる習慣を。たとえ曇りでも、室内照明とは比べ物にならないほど脳に刺激を与え、セロトニン分泌を促します。
② “軽い運動”でセロトニン活性化
特におすすめなのが朝のストレッチやウォーキング。運動することで「セロトニン」「ドーパミン」「ノルアドレナリン」といった神経伝達物質が分泌され、心の安定につながります。
③ 気圧アプリで“心構え”を整える
気圧の急な変化に備えて、天気・気圧変動がわかるアプリを活用。事前に気圧の低下がわかれば、無理な予定を入れず余裕をもった行動が可能に。自分の「気圧ストレスの傾向」も見えてきます。
⸻
◆ 子育て中・仕事中でもできる!“心をほぐす小さな習慣”
状況
対策
子育て中
子どもと一緒に深呼吸やお散歩を。セロトニン活性に◎
オフィス勤務
昼休みに窓際で光を浴びながら5分間の瞑想
家事の合間
アロマを炊いて深呼吸(ラベンダーやオレンジがおすすめ)
◆ まとめ:天気のせいにしてOK。心と上手につきあう6月へ
気圧や天候の変化で気分が落ち込んでしまうのは、決してあなたのせいではありません。
「天気が崩れると心が揺らぐのは自然なこと」と受け入れながら、心に優しいライフスタイルを選ぶことが、この時期を快適に過ごす第一歩です。
心の調子を崩しやすい梅雨時こそ、「環境に振り回されない習慣づくり」で、少しずつ“自律神経のリズム”を整えていきましょう。
第5章:女性の味方!自律神経を整えるライフスタイル術
梅雨時期の不調に悩まされる女性は多くいます。
「寝ても疲れがとれない」「イライラしやすくなる」「むくみやすい」…これらの背景には、自律神経の乱れが深く関係しています。特に女性はホルモンバランスと連動して自律神経が揺らぎやすく、天候や気圧の変化に敏感な傾向にあるため、意識的なケアが必要です。
この章では、自律神経を整える女性向けの生活習慣や具体的なセルフケア方法をご紹介します。
⸻
◆ 女性は自律神経が乱れやすい?3つの理由
1. 女性ホルモンの周期的変動
エストロゲンやプロゲステロンの分泌量が変化することで、交感神経と副交感神経のバランスが影響を受けやすくなります。
2. 感情と環境の影響を受けやすい
女性は感受性が高く、気圧や温度、湿度、音、においなどの外的ストレスが心身に作用しやすいとされています。
3. 多重タスクの負担
家事・育児・仕事などを同時にこなす女性は、常に交感神経が優位になりやすく、リラックスしにくい生活になりがちです。
⸻
◆ 今日からできる!女性におすすめの自律神経セルフケア
① 朝のルーティンでリズムを作る
• 起きたらすぐ日光を浴びる:セロトニン分泌を促進し、自律神経を目覚めさせる
• 白湯をゆっくり飲む:内臓を温めて副交感神経を優位に
② 「低気圧に負けない」体づくり
• ウォーキングやストレッチ:血流改善により自律神経が整いやすくなる
• 入浴で“リセット”:38〜40度のぬるま湯に15分が理想。リラックスホルモンを促進
③ 食生活で自律神経を応援する
栄養素
働き
おすすめ食品
マグネシウム
神経の興奮を抑える
ほうれん草・ナッツ類・納豆
ビタミンB群
神経伝達をスムーズにする
豚肉・卵・玄米
トリプトファン
セロトニンの材料
バナナ・豆乳・チーズ
◆ 忙しい女性でもできる“ながらケア”のすすめ
• 通勤中:呼吸を意識し、ゆったり深呼吸
• 仕事中:30分ごとに首や肩をまわすストレッチ
• 家事中:アロマディフューザーでリラックス空間を演出
こうした**小さな“自律神経メンテナンス”**の積み重ねが、6月の不調予防につながります。
⸻
◆ 特に意識したい「月経前後」の自律神経ケア
梅雨時期に加えて、PMS(月経前症候群)や生理中のホルモン変化が重なると、心と体の不調がより強く現れがちです。
• PMS期は「ゆるめる時間」を意識的に確保
• 無理な運動は避け、ヨガや深呼吸など穏やかな活動を
• 温活(カイロ・湯たんぽ・白湯)で副交感神経を優位に
⸻
◆ 女性が“調子いい私”でいられる6月へ
自律神経が安定すれば、心も身体も軽くなり、6月をより心地よく過ごすことができます。
日々の生活の中で「ちょっとした習慣」を意識するだけで、気圧にも天候にも揺らがない自分に近づくことができます。
自分の体と心をいたわることは、自分を大切にする第一歩です。
「今日一日、自律神経を整えるためにどんなことができるかな?」
そんな問いかけから、6月の毎日を整えていきましょう。
第6章:“気象病”対策に効く!6月に取り入れたい運動習慣
6月になると、「なんとなく体が重い」「頭がズキズキする」「気分が落ち込む」といった不調を感じる方が増えます。
このような症状の原因のひとつが、**「気象病(天気痛)」**です。
特に気圧の変化に敏感な人は、自律神経が乱れやすく、さまざまな不調に悩まされがちです。
しかし、適切な運動を日常生活に取り入れることで、自律神経のバランスを整え、気象病の症状を軽減することができます。
この章では、6月の不調対策としておすすめの運動習慣をご紹介します。
⸻
◆ 気象病とは?6月に多い“天気の不調”の正体
「気象病(天気痛)」とは、気圧・温度・湿度などの変化が体調に影響を与える現象の総称です。
特に梅雨の時期は低気圧が続くことで、自律神経が乱れ、血流が悪くなり、痛みや倦怠感、めまい、頭痛などが起きやすくなります。
こうした不調に対して、運動は“自然な処方箋”として非常に効果的なのです。
⸻
◆ 運動が自律神経に与える3つの好影響
効果
内容
解説
自律神経の調整
交感神経と副交感神経の切り替えがスムーズに
気圧変化に強い身体を作る
血流の促進
筋肉のポンプ作用で全身の循環が改善
むくみや冷えの予防にも有効
ストレス軽減
脳内ホルモン「セロトニン」「エンドルフィン」分泌
気分の落ち込みを予防・改善
特に、**深く呼吸しながら行う運動(有酸素運動)**は、リラックス神経である副交感神経を優位にし、梅雨の“なんとなくだるい”を改善します。
⸻
◆ 6月にぴったり!おすすめの運動習慣
① 朝のウォーキング(20〜30分)
• 太陽光を浴びて体内時計をリセット
• セロトニンの分泌を促して気分もすっきり
• リズム運動により自律神経のバランスを調整
※雨の日は室内で足踏み運動や踏み台昇降を代用しましょう。
② 軽めの筋トレ(週2〜3回)
• スクワット、プランクなど自重トレーニングでOK
• 筋力を維持することで血流がよくなり、冷えやむくみにも効果的
• 成長ホルモンの分泌が促され、疲労回復にも役立つ
③ ヨガやストレッチ(毎日10分でもOK)
• ゆっくりした動きと深い呼吸で副交感神経を優位に
• 首・肩・背中・骨盤まわりをゆるめて血行促進
• 寝る前のストレッチは睡眠の質向上にも◎
⸻
◆ 忙しい人向け「ながら運動」アイデア
• 歯磨き中にかかとの上げ下げ運動
• テレビを見ながら太ももやお尻のストレッチ
• 子どもと一緒に遊びながらスクワットや柔軟体操
無理をせず「続けられること」を第一に考え、日常の中に自然と運動を取り入れる工夫をしましょう。
⸻
◆ 女性のための“雨の日運動メニュー”
状況
おすすめ運動
効果
雨の日の朝
室内ウォーキング、ラジオ体操
セロトニン活性・気分転換
仕事終わり
お風呂後のストレッチ・ヨガ
緊張をほぐし睡眠の質UP
子どもが寝た後
動画を見ながらピラティス
呼吸と連動して体幹を整える
◆ 運動で「天気に左右されない自分」になる
6月の気圧や湿度に左右されることなく、自分らしく心地よく過ごすためには、継続できる運動習慣の構築が欠かせません。
「運動=つらい」「続かない」と思いがちな人も、1日5分からでもOK。
“やらなきゃ”ではなく、“心地いいからやりたい”という気持ちで取り組める運動が、あなたの毎日を支えてくれます。
第7章:腸を整えて気分もすっきり!“腸活”で自律神経をサポート
6月の梅雨時期は、気圧や湿度の影響で自律神経が乱れやすく、なんとなく「気分が重い」「イライラする」「眠れない」といった不調を感じる方が多くなります。
このような不調を根本から改善するために、近年注目されているのが**「腸活」**です。
腸内環境を整えることで、実は自律神経の働きや心の安定にも良い影響を与えることが分かってきています。
ここでは、気象の変化に負けない心と体をつくるための「腸活メソッド」をご紹介します。
⸻
◆ 腸と自律神経、実は“脳より深い関係”がある?
「腸は第二の脳」と呼ばれるように、腸と脳は**腸脳相関(ちょうのうそうかん)**という密接なつながりを持っています。
• 腸には 自律神経が集中しており、腸内環境が悪化すると神経の働きにも影響
• 腸内でつくられる**幸せホルモン「セロトニン」**は、その約90%が腸で生成される
• ストレスや不安による不調は、腸の働きを悪化させ、さらに自律神経が乱れるという悪循環に
つまり、腸の調子を整えることは、自律神経を整える近道でもあるのです。
⸻
◆ 梅雨におすすめの「腸活習慣」5選
① 発酵食品を日常に取り入れる
• 納豆、味噌、キムチ、ヨーグルトなど
• 善玉菌を増やして腸内フローラを整える
• 朝食にヨーグルト+バナナ、夜ごはんにお味噌汁を加えるなど手軽に実践可能
② 食物繊維を意識して摂る
• 不溶性:野菜(ごぼう・ブロッコリー)、きのこ、豆類
• 水溶性:わかめ、寒天、オクラ、納豆
• 善玉菌のエサになり、腸内の発酵を助ける
③ 腸を冷やさない食べ方を心がける
• 梅雨の時期は冷たい飲み物・アイスの摂りすぎで腸の働きが鈍くなる
• 常温の水、お味噌汁、生姜入りのお茶など、腸を温める飲食が効果的
④ 毎朝の排便リズムを整える
• 同じ時間にトイレに座る習慣をつける
• 起床後に白湯を飲む・軽くお腹をマッサージするのも◎
• 朝の排便習慣が自律神経のリズムを整える第一歩に
⑤ 適度な運動で腸を刺激する
• ウォーキングやヨガなど、リズミカルな運動が腸のぜん動運動を促進
• お腹周りの筋肉が動くことで、便通の改善にもつながる
⸻
◆ 6月に意識したい「腸活食材」10選
食材
効果
取り入れ方
納豆
発酵パワーで腸を活性化
朝ごはんやおにぎりに
ヨーグルト
善玉菌を直接補える
毎日の習慣に
バナナ
食物繊維とオリゴ糖が豊富
朝食やおやつに
キムチ
植物性乳酸菌が腸を元気に
豆腐や炒め物に添えて
わかめ
水溶性食物繊維で腸内を掃除
お味噌汁や酢の物に
もち麦
プレバイオティクスの宝庫
ご飯に混ぜて炊く
オクラ
ネバネバ成分で腸粘膜を保護
冷やしうどんにトッピング
ブロッコリー
不溶性食物繊維が豊富
蒸してサラダやおかずに
味噌
善玉菌を増やす日本の発酵食品
味噌汁は毎日でもOK
ぬか漬け
乳酸菌たっぷりで整腸作用
おにぎりや副菜に
◆ 心と体に効く「腸活レシピ」アイデア
• バナナヨーグルトスムージー(朝):朝のセロトニン活性に◎
• もち麦入り味噌汁(昼):腸も温まり、満足感もUP
• 納豆キムチごはん(夜):善玉菌と食物繊維の最強コンビ
• 生姜わかめスープ(夜食・寒い日):内臓を温めて深い眠りを促進
⸻
◆ 腸活で6月の心身をリセット!
梅雨の時期に乱れがちな自律神経は、薬やサプリだけで整えるのではなく、食事という毎日の積み重ねから整えることが可能です。
「腸が整うと気持ちも整う」というのは、実は科学的にも裏付けのある事実。
まずはできることから。朝のヨーグルトからでも、夜の味噌汁からでも構いません。
“腸が喜ぶ習慣”が、気圧の不調や梅雨のモヤモヤを根本から改善してくれます。
次章では、さらに「睡眠の質を高める梅雨時の夜の過ごし方」について解説していきます。
第8章:質の良い睡眠で回復力アップ!梅雨の夜の快眠メソッド
梅雨の時期は、気圧や気温の変化、湿度の高さによって眠りが浅くなる・寝つけない・途中で起きるといった睡眠の悩みを感じる人が増えます。
実はこれも、自律神経の乱れが大きな要因。特に副交感神経がうまく働かないと、眠っても疲れが取れにくく、日中の不調が長引くことに…。
この章では、梅雨にありがちな睡眠の質低下を防ぐための、具体的な快眠メソッドをご紹介します。
⸻
◆ なぜ梅雨は「よく眠れない」のか?その原因を解説
1. 気圧の低下による自律神経の乱れ
• 副交感神経(リラックス)よりも交感神経(緊張)が優位になりやすくなる
• 眠るべき夜に「交感神経ON」のままで寝つけない
2. 湿度が高く寝苦しい
• 湿度70%以上は「寝室が不快」なライン
• 寝汗・布団のムレが睡眠を浅くする
3. 寝る直前のスマホやブルーライト
• 光刺激で脳が覚醒状態に → メラトニン(睡眠ホルモン)分泌が抑えられる
⸻
◆ 快眠のために意識すべき「3つの要素」
要素
内容
理想的な対策
室温
快眠に最適なのは26℃前後
エアコンを「冷房ではなく除湿」に設定
湿度
50〜60%が理想
除湿器 or エアコンのドライ機能活用
光
薄暗さが副交感神経を刺激
間接照明・暖色系の電球を選ぶ
◆ 梅雨の夜におすすめの快眠ルーティン5選
① 寝る1時間前から「デジタルデトックス」
• スマホやPCを手放し、脳に“夜モード”を認識させる
• 替わりに、読書やストレッチ、アロマでリラックス
② 入浴はぬるめで15分。40℃以下がベスト
• 熱すぎると交感神経が活性化して逆効果に
• 入浴→リラックス→体温低下→眠気、という自然な流れをつくる
③ 就寝前の「深呼吸」や「瞑想」で副交感神経を優位に
• 4秒吸って、7秒止めて、8秒かけて吐く「4-7-8呼吸法」などが効果的
• 寝室でアロマ(ラベンダー、カモミール)を使うとより快適に
④ 腸を冷やさない軽めの夜食で“ぐっすり”
• 寝る直前の空腹も満腹も、どちらも睡眠の妨げに
• 温かいスープ・バナナ・ホットミルクなどが◎
⑤ 起きる時間は休日でも「固定」する
• 睡眠の質を高めるには「就寝時間」よりも「起床時間」の固定がカギ
• 平日+休日で朝の起床時間がズレると、自律神経のバランスが崩れる
⸻
◆ 快眠をサポートする栄養素&食材
栄養素
働き
含まれる食材
トリプトファン
セロトニン→メラトニンの材料
大豆製品、バナナ、卵
ビタミンB6
セロトニンの合成を助ける
まぐろ、鮭、にんにく
マグネシウム
神経の興奮を抑える
ナッツ、玄米、ひじき
GABA
リラックスを促す神経伝達物質
発芽玄米、トマト、カカオ
※夕食時に意識的に摂取することで、眠りの質がぐっと上がります。
⸻
◆ どうしても寝られない夜は?
• 一度ベッドを出て、間接照明の下で静かに過ごす
• 無理に寝ようとせず、「眠くなったら戻る」ことがポイント
• 白湯やノンカフェインハーブティー(カモミール、レモンバーム)がおすすめ
⸻
◆ まとめ:快眠こそが自律神経の“回復スイッチ”
睡眠は、乱れた自律神経をリセットし、体と心を回復させる唯一の時間です。
梅雨で不安定な季節こそ、「よく眠ること」が何よりの不調対策。
無理に完璧を目指さず、今日できることから1つでも習慣にするだけで、翌朝の目覚めや気分が変わってきます。
次章では、6月の不調に打ち勝つ「朝の過ごし方と1日のリズムの整え方」についてご紹介します。
第9章:朝のリズムが1日を決める!梅雨時期の“快適モーニング習慣”
梅雨の季節、朝起きてもスッキリせず「重だるい」「やる気が出ない」と感じる方も多いのではないでしょうか?
その原因の一つは、自律神経のリズムが夜だけでなく朝から崩れてしまっていることです。
実は、自律神経は“朝のスタート”によってその日のバランスが決まるといっても過言ではありません。
ここでは、6月の不調を防ぐためにぜひ取り入れてほしい、朝の整え習慣をご紹介します。
⸻
◆ 梅雨時期の朝にありがちな不調とは?
• 頭が重い・痛い(気圧による偏頭痛)
• 寝ても疲れがとれない
• 胃腸が動かない
• 気分が沈みがち
これらはすべて、「交感神経がうまくスイッチオンできていない」ことによるサイン。
つまり、“朝の目覚め”の質が悪いほど、自律神経は一日中うまく働きません。
⸻
◆ 朝の自律神経を整える「3つのポイント」
① 起きたらまず“太陽の光”を浴びよう
• 朝日を浴びるとセロトニンという“幸せホルモン”が分泌され、心身のスイッチが入る
• カーテンを開け、最低5〜10分、自然光を浴びることを習慣に
※曇りや雨の日でも、自然光の明るさは蛍光灯の数倍のパワーがあります。
② コップ一杯の白湯or常温の水を飲む
• 眠っている間に失われた水分を補給することで血流が良くなり、体が目覚める
• 冷たい水は胃腸を冷やすので、梅雨の朝には不向き
③ 軽く身体を動かす(朝ストレッチ・深呼吸)
• 呼吸や筋肉の刺激によって交感神経が活性化
• 全身の巡りが良くなり、眠気やだるさがリセットされる
おすすめは「ラジオ体操第1」や「太陽礼拝(ヨガ)」など、無理のない全身運動です。
⸻
◆ 朝食は“軽くても良いから必ず食べる”
自律神経を整えるためには、朝食による胃腸の刺激もとても重要です。
以下のような「梅雨にやさしい朝食メニュー」がおすすめです。
食材
自律神経に嬉しい効果
バナナ
セロトニンの材料「トリプトファン」を含む
オートミール
腸を整える食物繊維が豊富
ヨーグルト
腸内環境をサポートし、免疫力アップ
味噌汁
温かさ&発酵パワーで内臓が目覚める
卵
脳や神経に必要な栄養(コリン、B群)が豊富
※どうしても食欲がない日は「バナナ1本+ホット豆乳」などのミニセットでもOK。
⸻
◆ 朝のNG習慣に注意!
NG習慣
なぜNG?
スヌーズを何度も使う
自律神経のリズムが乱れ、余計に疲れる
起き抜けにスマホチェック
情報過多で交感神経が急に刺激され、ストレスに
冷たい飲み物
胃腸が冷えて、1日中だるくなりやすい
◆ まとめ:朝が変われば、梅雨の不調も変わる!
梅雨のどんよりとした空気に負けないためには、1日のスタートを「整える」ことが最優先です。
朝の5〜10分の行動が、自律神経を助け、気分や体の調子を大きく左右します。
まずは「光を浴びて水を飲む」「体を軽く動かす」など、簡単なことから始めてみてください。
次の章では、日中の過ごし方や気分の落ち込みを軽減する「リフレッシュ&リカバリー習慣」についてご紹介します。
第10章:日中の“だる重さ”対策!気分も体もリセットする過ごし方
梅雨の時期は、朝起きてから夕方までずっと「だるい」「重い」「集中できない」と感じる人も少なくありません。
これは、気圧変化による自律神経の乱れに加え、湿度の高さによって体が熱を放出しにくくなっていることが原因の一つです。
この章では、日中の不調を和らげるための具体的な過ごし方をご紹介します。
⸻
◆ “だるさの正体”は脳と血流のアンバランス
梅雨の湿気や低気圧は、自律神経のうちの副交感神経が優位になりすぎる傾向があります。
その結果、以下のような状態になりやすくなります。
• 眠くなる
• 頭がぼんやりする
• 気持ちが沈む
• やる気が出ない
• 肩や首が凝る
この“なんとなく調子が悪い”を改善するには、交感神経を適度に活性化させてバランスをとることが必要です。
⸻
◆ 日中のリフレッシュ&リカバリー習慣5選
① 1時間に1回は立ち上がって伸びをする
長時間座っていると、血流が滞り自律神経がさらに乱れます。
1時間に1回は意識して立ち上がり、背筋を伸ばす・肩を回す・深呼吸するの3セットを意識してみましょう。
② カフェインは朝〜昼までに。午後は控えめに
カフェインは交感神経を一時的に刺激する作用がありますが、午後以降の摂りすぎは自律神経のリズムを乱す原因になります。
午後はハーブティーや白湯、カフェインレス飲料がおすすめです。
③ ランチ後の軽いウォーキング
食後の軽いウォーキングは、血糖値の安定・腸の働き促進・自律神経の活性化など、嬉しい効果が盛りだくさん。
外に出にくい日は、室内で足踏みやラジオ体操でもOKです。
④ 天気に合わせて「明かり」を調整
梅雨は日中でも暗くなりやすいため、室内の明るさが気分に影響します。
やる気が出ない日は、あえてデスクライトや間接照明を明るめに設定すると、交感神経が刺激されて頭がスッキリします。
⑤ 香りの力を味方にする
アロマオイルやハーブの香りは、五感を通じて自律神経に働きかけてくれます。
特におすすめの香りはこちら:
香り
主な効果
レモングラス
リフレッシュ・気分転換に◎
ペパーミント
頭痛・集中力低下に◎
ラベンダー
緊張をほぐし、心をリセット
柑橘系(オレンジ・グレープフルーツ)
明るく前向きな気持ちに
◆ 梅雨こそ「昼寝のすすめ」
昼食後、どうしても眠気やだるさが取れないときは、10~15分程度の昼寝を取り入れるのも有効です。
この“パワーナップ”は、脳の疲労回復や集中力アップに効果的。
ただし、30分以上寝てしまうと深い睡眠に入り、起きたときに逆にだるさが残るので注意が必要です。
⸻
◆ デスクワーク中でもできる!“ながら”自律神経ケア
シーン
ケア方法
パソコン作業中
足の指をグーパーする/耳を軽くマッサージ
会議中
背筋を伸ばす/肩を回す(バレない範囲で)
トイレ休憩時
深呼吸+軽いスクワット3回
ちょっとした動作が、自律神経にとっては大きな刺激になります。
「ながらケア」を習慣にするだけで、午後のパフォーマンスがぐっと上がります。
⸻
◆ まとめ:こまめなリズム調整が梅雨の1日をラクにする!
梅雨の体調不良を一日中引きずらないためには、「朝しっかり目覚める→日中こまめに整える→夜しっかり休む」のサイクルがカギです。
特に日中の不調は、少しの意識と工夫で大きく軽減できます。
お気に入りの香りや音楽、明るい光など、自分に合ったリセット方法をぜひ見つけてみてください。
第11章:夜の“整え習慣”で自律神経をクールダウン
梅雨の夜は、湿気や気圧変動の影響で交感神経がなかなかオフにならず、「寝つけない」「眠りが浅い」「夜中に目が覚める」といった不眠トラブルが増える傾向にあります。
そこでこの章では、1日の終わりに自律神経をやさしく整える“夜の整え習慣”をご紹介します。
⸻
◆ なぜ梅雨の夜は眠りにくい?
1日の疲れを癒すはずの夜。にもかかわらず、
• 頭が冴えて眠れない
• 足がむずむずする
• 夜中に何度も目が覚める
といったことが起きやすいのは、自律神経が「オンモード」のままになっているからです。
特に梅雨時期は、湿度や気温の変化、日照不足により、副交感神経への切り替えがうまくいかないことが原因です。
⸻
◆ “夜の過ごし方”が翌日の体調を左右する
質のよい睡眠は、体と心の回復に不可欠。
とくに副交感神経を優位にするような夜の過ごし方が、梅雨の不調改善につながります。
⸻
◆ 寝る前30分でできる!「整え習慣」6選
① お風呂は38〜40℃で15分のぬるめ入浴
熱すぎるお湯は交感神経を刺激してしまいます。ぬるめのお湯で副交感神経を活性化し、体と心をゆるめてあげましょう。
入浴剤はラベンダーやカモミールの香りがおすすめ。
② 照明を暗めにして「夜の光環境」を整える
寝る1時間前からは、スマホやテレビのブルーライトを避けて照明を間接照明やオレンジ系に切り替えると、体が自然とリラックスモードになります。
③ 就寝前のストレッチで自律神経をリセット
硬くなった筋肉をほぐすことで、副交感神経が優位になります。特に肩甲骨まわり・股関節・背中を意識すると効果的。
④ 寝る前の“深呼吸”で心拍を落ち着かせる
5秒かけて吸って、5秒かけて吐く「ゆっくり深呼吸」は、交感神経から副交感神経へのスイッチを助けます。
ストレスを感じた日の夜は、呼吸を整えることが最高のセルフケアになります。
⑤ アロマ・ハーブティーで五感から整える
寝る30分前に温かいハーブティー(カモミール・ルイボスなど)を飲んだり、アロマディフューザーで好みの香りを焚くのもおすすめ。
嗅覚は自律神経と直結している感覚なので、心と体にじんわり効きます。
⑥ 寝具とパジャマは“肌触り”と“通気性”重視
梅雨は意外と寝苦しく、寝汗で眠りが浅くなることも。
寝具は吸湿性・通気性に優れたもの、パジャマは綿やガーゼ素材が理想です。快適な睡眠環境づくりが、自律神経のクールダウンを助けます。
⸻
◆「脳内おしゃべり」を止めたいときの対処法
眠る前に今日の反省や明日の心配ごとが頭をグルグル…そんな「脳内おしゃべり」で眠れないときは、
• 紙に書き出して“頭の外に出す”
• 好きな香りで気分を切り替える
• 呼吸だけに意識を向ける「マインドフルネス」
といった方法が効果的です。とくに書き出す作業は「脳の整理」として非常におすすめです。
⸻
◆ 翌朝の「すっきり目覚め」は、夜の準備から
質のよい睡眠がとれると、朝の目覚めも軽く、1日をポジティブに始めることができます。
夜の習慣を整えることは、梅雨の自律神経ケアの総仕上げです。
無理のない範囲で、自分に合った“整え習慣”を取り入れてみましょう。
第12章:梅雨の不調に効く!食事で整える体と心
梅雨の体調不良は、「気圧や湿度」など外的要因によって引き起こされるものが多いですが、それに打ち勝つカギは、**内側から整える“食事の力”**にあります。
特にこの時期は、自律神経のバランス・むくみ・冷え・気分の落ち込みといったトラブルが目立つため、それらにアプローチできる食材や栄養素を意識的に取り入れることが重要です。
⸻
◆ 梅雨の体と心に効く!おすすめ栄養素&食材5選
①【ビタミンB群】:エネルギー代謝をサポートし、疲労回復にも◎
自律神経の働きを助け、脳や神経のストレス耐性を高める効果があります。
特に梅雨は「だるさ」や「眠気」が出やすいため、ビタミンB1・B6の摂取がおすすめ。
多く含まれる食品:
• 豚肉
• 納豆
• 卵
• 玄米
• まぐろ
②【マグネシウム】:神経の興奮を抑え、心を落ち着ける
自律神経のバランスを保ち、不安感やイライラを鎮めるミネラルです。
多く含まれる食品:
• アーモンド
• ひじき
• 豆腐
• バナナ
• 玄米
③【カリウム】:体の水分バランスを整え、むくみ対策に
湿気が多い梅雨は、汗が出にくく、体内の水分が停滞しがち。カリウムは余分な水分を排出し、むくみやだるさの解消をサポートします。
多く含まれる食品:
• きゅうり
• アボカド
• スイカ
• トマト
• 里芋
④【トリプトファン&ビタミンB6】:セロトニンの材料に
“幸せホルモン”と呼ばれるセロトニンは、気分の安定に欠かせません。トリプトファンとビタミンB6のセットでの摂取が効果的。
多く含まれる食品:
• バナナ
• チーズ
• 鶏むね肉
• 大豆製品
⑤【食物繊維&発酵食品】:腸内環境を整え、免疫&気分にアプローチ
腸と脳はつながっており、「腸が整う=メンタルが安定する」と言われるほど。腸活に効果的な食事を意識しましょう。
多く含まれる食品:
• きのこ類
• わかめ
• ヨーグルト
• キムチ
• 納豆
⸻
◆ 忙しい人にもおすすめ!梅雨の時短食事アイデア
• 朝食にバナナ+ヨーグルトでトリプトファン補給
• 昼は豚しゃぶサラダでビタミンB群とカリウム補給
• 夜は豆腐や納豆、雑穀米を使った腸活定食スタイル
• 間食には素焼きアーモンドやゆで卵で栄養チャージ
無理なく、“ちょい足し”感覚で栄養素を取り入れることが、継続のコツです。
⸻
◆ 「冷たい食べ物」に注意!体を冷やしすぎない工夫を
梅雨は冷たい飲み物・アイス・冷房などで内臓が冷えがち。内臓の冷えは代謝の低下・自律神経の乱れにもつながります。
• 冷たいものを取るときは、温かい汁物や常温の飲み物をセットに
• 夏野菜でも、加熱することで体を冷やしにくくできる
• 生姜・にんにく・ネギなどの“温め食材”も活用
⸻
◆ 1日3食、心と体の「バランス補給」を意識しよう
梅雨の時期は、食事の内容次第で体調が大きく左右される季節です。
乱れがちな心身を支える“栄養”は、最も身近なセルフケアのひとつ。
• 栄養の偏りを防ぐ
• できる範囲で手作りに
• よく噛んでリラックスホルモンを出す
こうした意識が、日々の健康を大きく支えてくれます。
第13章:6月の不調を防ぐ!1週間でできる“体質改善チャレンジ”
梅雨の季節は、知らず知らずのうちに心身のバランスが崩れやすくなります。でも、毎日少しずつ生活習慣を整えるだけで、自律神経は確実にリセットされ、体調も前向きに変化していきます。
ここでは、1週間で実践できる「体質改善プログラム」をご提案します。無理なく、自分のペースでOKです!
⸻
◆ 月曜日:リズムを整える朝活スタート
• 朝日を浴びる習慣をつける(5〜10分でもOK)
→ セロトニン分泌で、自律神経がリセット
• 朝食にバナナ+ヨーグルト+白湯で腸&脳を起こす
• 朝のストレッチで“巡り”を促す(5分間で十分)
☑目標:「梅雨バテのスタートを防ぐ体内リズム作り」
⸻
◆ 火曜日:“むくみ”対策の食習慣を意識
• 昼食にカリウム豊富な食材(アボカド、きゅうり、トマト)を取り入れる
• 夜は湯船に10〜15分浸かって、代謝UP+デトックス
• 水分は「こまめに常温」で摂取
☑目標:「体に溜まった水分をリセットし、巡りやすい体に」
⸻
◆ 水曜日:腸を元気にする“腸活DAY”
• 朝食や夕食に発酵食品(納豆・キムチ・みそ汁など)を1品追加
• 食物繊維の摂取(きのこ・海藻・ごぼうなど)で腸内環境を整える
• 軽いウォーキングや足裏マッサージで腸を刺激
☑目標:「腸から整え、気分の落ち込みや便秘もケア」
⸻
◆ 木曜日:冷え対策&“温め食”を意識
• 昼食・夕食に温かいスープや味噌汁、根菜料理を取り入れる
• 生姜、ネギ、にんにくなど“体を温める食材”を活用
• 足元を冷やさない服装や靴下で“冷え取り”を
☑目標:「内臓の冷えを防ぎ、自律神経の安定を図る」
⸻
◆ 金曜日:ストレスオフで“脳疲労”回復
• スマホ・PCから1時間だけ“デジタルデトックス”
• 好きな音楽・アロマで副交感神経を活性化
• 寝る前に3分間深呼吸+ストレッチ
☑目標:「心をゆるめて、週末に向けて回復力をチャージ」
⸻
◆ 土曜日:外に出て“太陽と運動”でリフレッシュ
• 晴れた日は短時間でも外出&ウォーキングを
• 植物や自然に触れる“グリーンセラピー”もおすすめ
• 家で軽い筋トレやストレッチでもOK(運動初心者にも◎)
☑目標:「体を動かして自律神経をアクティブに整える」
⸻
◆ 日曜日:自分をねぎらう“ご褒美デー”
• 好きなものを食べたり、趣味に没頭する時間を確保
• 日記やメモで「1週間やったこと」を振り返ってみる
• 次週のための“生活リズムメモ”を残しておく
☑目標:「心の疲れを癒やして、また一歩前へ」
⸻
◆ 続けるコツは「完璧を目指さないこと」
この1週間チャレンジは、“できたこと”に目を向けることが成功のカギです。
毎日全部やる必要はなく、1つでも取り組めたら大成功。続けるほどに、心と体がじわじわと整っていきます。
第14章:毎日をもっと快適に!気象に負けない“習慣力”の育て方
6月の不調を乗り切るためには、単発の対策だけでなく、「習慣」として身につけていくことが鍵になります。特に梅雨のような長期的な気象変化には、**“継続できる工夫”と“自分に合ったスタイル”**を持つことがとても重要です。
この章では、気象による不調に負けないための「習慣力の育て方」と、今日から実践できる“続けやすいヒント”をお届けします。
⸻
◆ 習慣力のカギは「ハードルの低さ」
最も大切なのは、最初から完璧を目指さないことです。
• 朝のストレッチ→1分だけでもOK
• 自律神経ケア→「深呼吸を3回」でもOK
• 腸活→週に2〜3回の納豆でもOK
「少しだけやる」「意識するだけでOK」——このように小さなハードルから始めると、習慣は自然に身につきます。
⸻
◆ 「○曜日には○○をする」ルーティン化で脳をラクに
曜日ごとのテーマを決めてしまうのも、梅雨時期の不調対策として有効です。
例:
• 月曜:朝の深呼吸+日光浴
• 火曜:発酵食品を取り入れる腸活デー
• 水曜:足湯+湯船につかる
• 木曜:ストレッチ+温活
• 金曜:デジタルデトックス+アロマ
• 土曜:外出ウォーキング
• 日曜:好きなことをする心のケア
「考えなくても動ける」状態をつくることで、習慣化がスムーズになります。
⸻
◆ 続けやすさUPのコツ3選
① 記録する(手帳やスマホメモでも◎)
• できたことを「○」で記録
• 続いていることが視覚化されてモチベUP
② 誰かとシェアする
• SNSで「今日は○○できました」と投稿
• 家族や友人に「続いてるよ」と報告
周囲とのつながりが「やる気スイッチ」に!
③ ごほうびを設定する
• 1週間続いたら、ちょっと良いスイーツ
• 1か月続いたら、気になっていた美容グッズ
“楽しみ”を組み合わせることで、継続はさらに楽になります。
⸻
◆ 習慣は“梅雨明け”後も効果的!
梅雨に整えた習慣は、そのまま夏の猛暑・秋の不調予防にも役立ちます。
• 自律神経が整って、夏バテしにくくなる
• 湿度の変化に慣れて、季節の変わり目に強くなる
• 心身の回復力が高まり、1年を通じて元気に
今この6月に始めたことが、未来のあなたの健康を守る“資産”になるのです。
⸻
◆ 習慣力はあなたの“最強の武器”になる
「何をするか」ではなく、「どう続けるか」が体調改善のカギ。
気象に左右されやすい時期こそ、小さなことをコツコツ積み重ねる習慣力が、あなたの体と心を支えてくれます。
第15章:まとめ|6月の体調不良は“予防”がすべて。今日からできるケアで快適な毎日へ
6月は、体も心もゆらぎやすい季節です。気圧の変化、梅雨による湿度や日照不足、そして寒暖差——。これらは、自律神経を乱れさせ、「なんとなく不調」を感じやすくする要因となります。
しかし、私たちの体は“ちょっとした心がけ”で変わります。6月の体調不良に振り回されないためには、「不調になってから対処する」のではなく、「日々の習慣で整える」こと、つまり予防こそが最も効果的なケアなのです。
⸻
▶︎ 6月の体調不良は“自律神経の乱れ”がカギ
このブログでご紹介してきたように、6月特有の不調の多くは「自律神経の乱れ」が原因です。以下のような症状、思い当たる方も多いのではないでしょうか?
• 朝起きられない、眠りが浅い
• 頭痛やめまいが頻繁に起こる
• 気分が落ち込みがち
• むくみやすく、体がだるい
• 食欲がわかない、胃腸の調子が悪い
これらは、すべて自律神経のバランスが崩れているサインです。そしてそのケアは、特別なことではなく、日常の中のシンプルな習慣で整えることができるのです。
⸻
今日から実践!6月の不調を防ぐ3つのゴールデンルール
① 「朝の光」と「リズム」で体内時計をリセット
朝起きたらカーテンを開けて自然光を浴びましょう。体内時計が整い、自律神経がスムーズに切り替わるようになります。毎朝決まった時間に起きる習慣も、自律神経の安定に直結します。
② 「腸活」と「栄養補給」で体の中から整える
腸は“第二の脳”とも呼ばれ、自律神経や気分に深く関係しています。食物繊維、発酵食品、ビタミンB群、マグネシウムなどを意識的に摂取し、腸内環境を整えましょう。
③ 「軽い運動」で心と体の巡りをよくする
ウォーキングやストレッチ、軽めのヨガなど、無理なくできる運動を日常に取り入れることで、血流がよくなり、自律神経が整います。運動は“天然の自律神経調整薬”とも言われています。
⸻
完璧を目指さなくてOK。「できることを1つだけ」始めることがカギ
「朝起きて窓を開ける」
「寝る前のスマホを5分だけ早くやめる」
「お味噌汁にわかめを足してみる」
…こんな小さなことの積み重ねが、自律神経のバランスを支え、6月を快適に過ごす土台となります。
完璧を目指す必要はありません。**大切なのは“続けられる”ことを、1つだけ選んで実行すること。**それがやがて、体調の安定と心の余裕へとつながっていきます。
⸻
雨の日も、気分が沈む日も。「ゆらぎに強い自分」を育てよう
6月は、一年の中でも特に不調が出やすい季節。でも裏を返せば、この時期をどう過ごすかが、今後の体調やメンタルを左右する大きな分かれ道でもあります。
今日からできる小さなケアで、あなた自身の「本来のリズム」を取り戻し、心地よい日常を手に入れましょう。
ゆらぎの季節を乗り越える力は、あなたの中にちゃんとあります。
あなたの6月が、心も体も軽やかに過ごせる毎日でありますように。