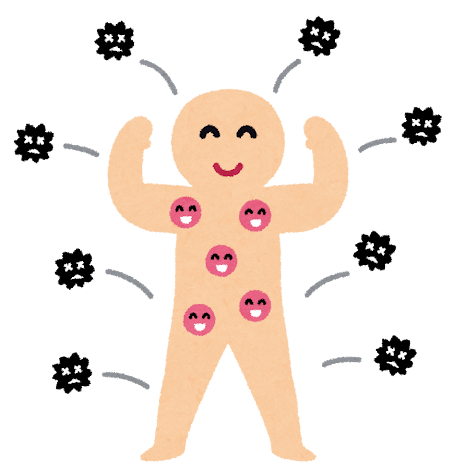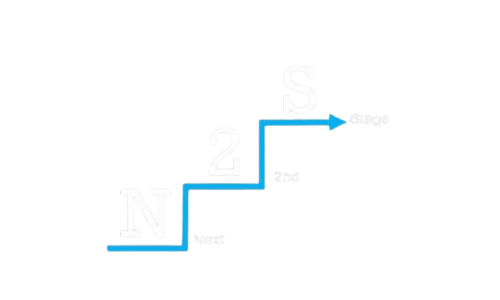NEWS
花粉症対策として腸活を推奨
2025.4.28
西宮門戸厄神 パーソナルトレーニングジムN2Sパーソナル トレーナーの中阪です!
今回の内容は、前回に引き続き花粉症にフォーカスをあて、特に「腸活」に着目してまとめてみました。
春の花粉のピークは過ぎたかもしれませんが、夏秋の花粉など、年中花粉症に悩まされる人も少なくありません。僕も春、秋と花粉症で苦しんでいます…。また、次シーズンの花粉症を少しでも和らげたい人は必見!来るべき「攻防戦」に備えて日頃から身体の調子を整え免疫UPを図りましょう!
筋トレで筋肉を鍛えることと同様に、身体の内側からしっかり鍛えてたくましくなりましょう。
花粉以外にも、様々なアレルギーや日頃の風邪など、免疫力を鍛えることで様々なカラダの不調とは無縁になりたいものですね。腸活という言葉も、最近では一般的ですがそのメカニズムも少しご理解いただける内容になておりますので、長文になりますが是非最後まで読んでみてくださいね!
第1章:花粉症とは? 〜その仕組みと近年の傾向〜
春になると、多くの人が「目がかゆい」「鼻水が止まらない」「くしゃみが連続で出る」といった不快な症状に悩まされます。これらの症状の多くは、「花粉症」と呼ばれるアレルギー性疾患が原因です。日本において特に多いのが、スギ花粉症であり、花粉の飛散時期である2月から4月にかけて多くの人に影響を与えています。
花粉症の仕組み
花粉症は、体内の免疫システムが花粉という異物に過剰反応することで起こるアレルギー反応の一種です。通常、免疫は細菌やウイルスなどの病原体に対して働きますが、アレルギー体質の人では本来無害であるはずの花粉を敵とみなしてしまい、体が攻撃を開始します。
このとき、体内では「ヒスタミン」と呼ばれる化学物質が分泌され、鼻の粘膜が腫れたり、涙腺が刺激されて涙が出たりといった反応が起こります。こうして鼻水、鼻づまり、目のかゆみ、喉のイガイガなどの症状が現れるのです。
日本人の約4割が花粉症持ち?
近年の調査によると、日本人の約40%が何らかの花粉症の症状を持っていると言われています(出典:環境省 花粉症環境保健マニュアル)。中でもスギやヒノキが代表的な原因植物として知られていますが、地域によってはイネ科やブタクサなど、他の植物の花粉によるアレルギーも増加しています。
特に都市部では、大気汚染やストレスなども影響して、症状が悪化する傾向があると指摘されています。
なぜ花粉症が増えているのか?
以下のような要因が、花粉症の増加に関係していると考えられています: • 都市部のコンクリート舗装:花粉が土に吸収されず、空中に再飛散しやすい。 • スギの植林政策:戦後に植えられたスギの木が成熟し、大量の花粉を放出するようになっている。 • 生活習慣の変化:食生活の欧米化、腸内環境の悪化、睡眠不足などが免疫バランスに影響している。 • 衛生仮説:あまりに清潔な生活環境が、免疫機能の過敏化を招いているという仮説。
子どもにも増えている花粉症
以前は大人に多いイメージがあった花粉症ですが、最近では幼児〜小学生の子どもにも増加しています。これは、遺伝的な体質に加え、食生活の乱れや運動不足、外遊びの減少などが背景にあるとされています。
子どもは自分の症状をうまく表現できないこともあるため、「鼻をいつもすすっている」「目をこする」「集中力が続かない」などの様子が見られたら、早めに耳鼻科などでの診察が推奨されます。
第2章:腸内細菌と免疫の関係 〜健康のカギを握る「腸内フローラ」〜
「腸は第二の脳」とも呼ばれるほど、腸は体の中で非常に重要な役割を果たしています。その理由の一つが、免疫機能の中枢としての働きです。そしてこの免疫機能と密接に関わっているのが、腸にすむ数百種類・数百兆個ともいわれる微生物たち、つまり腸内細菌です。
腸内フローラとは?
腸内に存在する微生物群は、「腸内フローラ(腸内細菌叢)」と呼ばれています。これは、さまざまな細菌がバランスを取りながら共存している状態を指します。ちょうど花が咲き乱れる「フローラ(flora)」=お花畑のように見えることから、この名がつきました。
腸内フローラには大きく分けて3つのタイプの菌が存在しています: • 善玉菌(ビフィズス菌、乳酸菌など):健康維持に貢献し、腸内を酸性に保つ。 • 悪玉菌(ウェルシュ菌、ブドウ球菌など):腸内で有害物質を作り出す。 • 日和見菌(バクテロイデスなど):環境によって善玉・悪玉のどちらにも傾く中間的な存在。
この3つの菌のバランスが健康状態に大きく影響を与え、特に善玉菌を多く保つことが腸内環境の理想とされています。
免疫細胞の約70%は腸に存在している!
私たちの体を守る免疫細胞のうち、約70%が腸に集中していることをご存知でしょうか?これは腸が体の中でもっとも外部と接触する器官であり、食べ物と一緒に入ってくる細菌やウイルスなどを見張る必要があるからです。
腸内細菌は、この免疫細胞の働きに大きな影響を与えており、善玉菌が豊富に存在する腸では、免疫が正常に働きやすくなるとされています。
逆に、悪玉菌が増えたり腸内フローラのバランスが乱れると、免疫機能が誤作動を起こし、アレルギー反応や自己免疫疾患の引き金になることがあります。
腸内環境とアレルギー体質の関係
花粉症をはじめとするアレルギー性疾患は、免疫の暴走(=過剰反応)によって引き起こされます。そのため、腸内環境が整っていれば、免疫の暴走が抑えられ、アレルギー症状が和らぐ可能性があります。
実際、腸内細菌のバランスが整っている人は、アレルギーの発症率が低いという研究報告もあり、乳酸菌やビフィズス菌といった**プロバイオティクス(有用菌)**の摂取によって、花粉症症状が軽減される例も報告されています。
ストレスと腸内環境の関係
また、ストレスや睡眠不足も腸内細菌のバランスに影響を与えることがわかっています。ストレスがかかると、自律神経が乱れ、腸の働きが鈍くなり、便秘や下痢を引き起こしやすくなります。これにより、悪玉菌が増えてしまい、腸内環境が悪化するという悪循環に陥ってしまうのです。
そのため、栄養バランスの良い食事だけでなく、規則正しい生活とストレスマネジメントも、腸と免疫の健康には欠かせない要素といえます。
第3章:腸内細菌と花粉症の関係 〜アレルギー症状を和らげる腸の力〜
前章で述べた通り、腸内環境と免疫機能は深く結びついており、それはアレルギー疾患の代表格である花粉症にも大きな影響を与えています。ここでは、なぜ腸内細菌が花粉症の発症や悪化に関与するのか、また改善のカギを握るのかを詳しく解説します。
腸内フローラとアレルギー反応の関係
私たちの免疫機能は、本来「必要な敵(ウイルスや細菌)」にだけ反応するよう設計されています。しかし、アレルギー体質の人の場合、この免疫の選別がうまくいかず、本来は無害な花粉にも過剰に反応してしまうのです。
この免疫の「過剰反応」を防ぐ役割を果たしているのが、腸内細菌のバランスです。
特に注目されているのが、「制御性T細胞(Treg細胞)」という免疫細胞です。これは、暴走しそうな免疫反応を抑える働きをしており、このTreg細胞の活性化には腸内細菌が深く関与しています。
近年の研究では、ビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌が腸内に多い人ほど、Treg細胞の働きが活発であることが分かってきました。つまり、善玉菌が豊富な腸内環境を維持することが、花粉症などのアレルギー反応を和らげる可能性があるのです。
花粉症と腸内環境の悪化要因
逆に、腸内環境が悪化するとどうなるでしょうか? • 加工食品や高脂肪・高糖質な食事 • 不規則な生活リズム • ストレス・睡眠不足 • 運動不足 • 抗生物質の過剰摂取
これらはすべて、腸内の善玉菌を減少させ、悪玉菌が優勢になる原因になります。悪玉菌が増えると、腸内で発生する有害物質が腸壁を刺激し、炎症や腸のバリア機能低下を引き起こすことがあります。これが全身の免疫暴走の引き金となり、花粉症の症状が重くなるリスクが高まると考えられています。
腸活による花粉症対策とは?
「腸活」という言葉が最近注目を集めていますが、これはまさに花粉症にも効果的な習慣です。以下のような食習慣が、腸内環境の改善に有効です。
1. 発酵食品を摂る
ヨーグルト、納豆、キムチ、味噌などの発酵食品は、善玉菌を直接摂取できる食品です。特に乳酸菌の中には、花粉症症状の軽減に役立つ種類もあることが分かっています(例:L-92乳酸菌など)。
2. 食物繊維をしっかりとる
腸内細菌のエサとなるプレバイオティクス(難消化性の食物繊維やオリゴ糖)を摂ることで、善玉菌の増殖が促進されます。野菜、きのこ、海藻、玄米などが豊富な食材です。
3. 食事リズムを整える
暴飲暴食や間食が多いと、腸内環境が乱れやすくなります。3食をバランスよく摂り、空腹の時間も設けることで、腸の自浄作用が働きやすくなります。
4. 水分をしっかり補給
水分不足は便秘を引き起こしやすく、それが腸内の悪玉菌の繁殖につながります。日常的にこまめな水分補給を心がけましょう。
腸と花粉症の未来:研究の最前線
現在では、腸内細菌の状態を**遺伝子解析(腸内フローラ検査)**でチェックし、個人に合った栄養やサプリメントを提案する医療やサービスも登場しています。将来的には「花粉症の重症度予測」や「症状の予防」まで腸内細菌を元に行えるようになると期待されています。
第4章:腸内環境を整える栄養素と食べ物 〜体の内側から花粉症対策〜
腸内環境を整えることは、花粉症だけでなく、全身の免疫バランスを保つ上でも極めて重要な要素です。ここでは、腸内環境を改善するために特に注目すべき栄養素と、それらを豊富に含む食品について詳しく解説します。
1. 発酵食品と乳酸菌
乳酸菌は腸内の善玉菌を増やし、免疫調整に働くため、発酵食品の摂取は腸内環境の改善に欠かせません。たとえば、ヨーグルト、納豆、キムチ、味噌などが挙げられます。
・ヨーグルト:毎朝の習慣として、無糖タイプのヨーグルトを摂ると、乳酸菌が安定して腸内環境を整え、免疫機能のサポートに寄与します。特にプロバイオティクスが含まれている製品は、花粉症の症状緩和に効果があるとされています。
・納豆:発酵大豆食品として、納豆は納豆菌が豊富に含まれており、善玉菌の増加に貢献します。さらに、納豆に含まれるビタミンK2やたんぱく質も免疫維持に役立ちます。
2. 食物繊維とプレバイオティクス
腸内細菌のエサとなる食物繊維は、プレバイオティクスとして善玉菌の栄養源となり、菌の増殖を促進します。
・全粒穀物と玄米:これらは食物繊維を豊富に含み、消化吸収の緩やかなエネルギー供給とともに、便通改善や腸内環境の正常化に寄与します。
・野菜と果物:ブロッコリーやキャベツ、にんじん、さらにりんごやキウイなどは、可溶性食物繊維も多く含むため、腸内に水分を保持し、滑らかな排便をサポートします。
3. ビタミンとミネラル類のサポート
ビタミンやミネラルは、腸の細胞を保護し、バリア機能を強化する働きがあります。
・ビタミンC:果物や緑黄色野菜に含まれるビタミンCは、抗酸化作用により腸内の炎症を抑える効果があります。また、鉄の吸収を助けるため、腸内環境の改善にプラスの影響を与えます。
・マグネシウム:ナッツ類、種子、海藻、豆類に含まれるマグネシウムは、腸の蠕動運動を促し、消化不良や便秘の予防に役立ちます。これにより、腸内の有害菌の繁殖を抑える環境が作られ、善玉菌の増加を支えます。
4. おすすめの実践的な食習慣
腸内環境を整えるためには、上記の栄養素をバランスよく摂取することが重要です。例えば、朝食にヨーグルトと全粒シリアル、昼食に野菜たっぷりのサラダと納豆入りの玄米ご飯、間食にフルーツとナッツを取り入れるなど、毎日の食生活に意識的な工夫をすることで、腸内環境が徐々に改善されていきます。また、規則正しい食事時間と十分な水分補給も、腸の働きを活発にするために欠かせません。 ⸻
このように、発酵食品、食物繊維、ビタミン・ミネラルのバランスを意識した食事は、腸内フローラを整え、免疫調節をサポートすることで、花粉症などのアレルギー症状の軽減に寄与します。生活習慣全体を見直す中で、これらの栄養素を意識的に取り入れることが、春の不調を和らげるための大きな鍵となるでしょう。
第5章:実践的な腸内細菌改善対策と生活習慣
腸内環境の改善は、花粉症やアレルギー症状の軽減に直結します。ここでは、日々の生活の中で実践できる対策を具体的にご紹介します。専門家が提唱する方法を取り入れることで、腸内フローラのバランスを整え、免疫の過剰反応を防ぐ効果が期待されます。
1. 規則正しい食事と水分補給
毎日3食、できるだけ同じ時間に食事を摂ることは、腸の自浄作用を助ける上で非常に重要です。不規則な食生活は、腸内細菌のバランスを崩し、悪玉菌が優勢になるリスクを高めます。また、水分摂取も重要です。十分な水分(1日1.5〜2リットル程度)を摂ることで、腸内での便通がスムーズになり、不要な老廃物の排出を促進します。
2. 発酵食品の積極的な摂取
前章でも触れた通り、ヨーグルト、納豆、キムチ、味噌などの発酵食品は、腸内に直接働きかける乳酸菌を供給します。特に、毎日の朝食や昼食にこれらの食品を取り入れると、継続的な腸内改善が図れます。 • ヨーグルト:プレーンタイプを選び、無糖で摂るのが基本です。フルーツやナッツを加えて、栄養バランスを整える工夫もおすすめです。 • 納豆:そのままご飯にかけたり、サラダにトッピングしたりすることで、手軽に摂取可能です。
3. 食物繊維の豊富な食材の活用
腸内細菌のエサとなる食物繊維は、善玉菌の増殖を促進します。玄米、全粒パン、オートミール、野菜、果物など、普段の食事に取り入れることで、腸の動きを活発にし、便秘の解消にもつながります。さらに、オリゴ糖やイヌリンなどのプレバイオティクスを含む食品も、腸内環境改善に非常に効果的です。
4. 定期的な運動とストレスマネジメント
運動は、腸内の血流を改善し、腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)を促します。ウォーキングや軽いジョギング、ヨガなど、無理なく続けられる運動を週に3〜4回行うとよいでしょう。また、ストレスは腸内細菌に大きな影響を与えるため、深呼吸、瞑想、趣味を楽しむ時間を設けるなど、心のリラックスも忘れてはいけません。十分な睡眠時間の確保も、腸内環境を整える上で大切な要素です。
5. 食生活の記録と見直し
日々の食事内容や体調の変化を記録することで、どの食品が自分にとって効果的か、どの生活習慣が腸内環境に良い影響を与えているかを把握できます。スマートフォンのアプリやノートを使って、食事日記をつけ、定期的に見直す習慣をつけましょう。そうすることで、自分自身にとって最適な腸活プランが見えてきます。
第6章:具体的な対策プランと事例紹介 〜自分に合った腸活で花粉症対策を実現する〜
ここまで、腸内細菌と花粉症、腸内環境を整える食生活・生活習慣の重要性について解説してきました。続いて、実際に取り入れやすい対策プランと、実例を基にした事例紹介をご提案します。自分に合った腸活(腸内環境改善)を実践するための具体的な手法として、以下の対策プランを参考にしてください。
1. 毎日の食事計画
まず、腸活の基本となるのは食生活の見直しです。以下のプランは、花粉症の症状緩和に向けた腸内環境改善に効果的な食品をバランス良く摂取するための例です。 • 朝食: • ヨーグルト(無糖タイプ)に、刻んだキウイやバナナ、ナッツをトッピング • オートミールをミルクまたは豆乳で煮込み、シナモンをかける
→ 発酵食品と食物繊維、ビタミンCを同時に摂取することで、朝から腸内環境を整えることができます。 • 昼食: • 玄米または全粒粉パンを主食にし、発酵食品としての納豆や味噌汁を組み合わせる • 野菜たっぷりのサラダを副菜にし、オリーブオイルとレモンでドレッシングを作る
→ 食物繊維と発酵食品が、腸内の善玉菌を増やす働きをサポートします。 • 夕食: • サバの水煮缶やサバの味噌煮をタンパク源として取り入れ、温野菜や根菜を添える • 乳酸菌が豊富な発酵漬物を少量プラス
→ オメガ3脂肪酸やミネラルも補え、全体的な栄養バランスが向上します。
2. ストレスケアと生活リズムの改善
食事だけではなく、生活全体の見直しも重要です。毎日のストレスが腸内環境に大きく影響するため、以下のポイントも意識してください。 • 規則正しい睡眠:
就寝時間と起床時間を固定し、十分な睡眠(7〜8時間)を確保することで、自律神経を整え、腸の働きを最適化します。 • 適度な運動:
朝の散歩やヨガ、ストレッチなど、無理なく続けられる軽い運動を週に3〜4回取り入れると、腸の蠕動運動が活発になり、消化吸収がスムーズになります。 • リラクゼーション:
瞑想や深呼吸、趣味の時間を取り入れ、ストレスを適切に解消することが、腸内環境の維持と全身の健康に寄与します。
3. 記録とフィードバック
実際に対策を始めた場合、日々の食事記録や体調の変化を記録することが大切です。例えば、スマートフォンアプリや手帳を使い、以下の内容をチェックします。 • 食事内容(摂取した発酵食品、食物繊維、ビタミン類など) • 便通の状態や体調の変化(花粉症の症状の程度、エネルギーレベルなど) • ストレスレベル、睡眠時間や運動量
これらのデータを元に、1週間ごと、または1ヶ月ごとに見直し、どの対策が効果的だったか、改善すべき点は何かをフィードバックすることが、長期的な腸活の鍵となります。
4. 事例紹介:実際に成果を上げた例 • 事例1:30代女性の事例
仕事のストレスと不規則な生活から、毎年春に花粉症と体のだるさに悩んでいたAさんは、毎朝のヨーグルトと全粒シリアル、昼食に玄米ベースの定食、夕食に魚中心のメニューに切り替えるとともに、週に2回のウォーキングを開始しました。1ヶ月後には、花粉症の症状が軽減し、翌春も症状の出現がかなり抑えられるようになったと報告されています。 • 事例2:40代男性の事例
慢性的な便秘と花粉症に悩むBさんは、納豆やキムチ、味噌汁などを積極的に食事に取り入れ、朝夕の決まった時間に食事と軽い運動(ストレッチや散歩)を行う生活にシフトしました。記録を続けた結果、腸内環境の改善が実感でき、花粉症の症状も和らいだとのことです。
5. 専門家のアドバイスを参考に
これらの対策プランは、医療・栄養、そして生活習慣改善の分野で実績のある専門家のアドバイスに基づいています。個々の体質や生活環境に合わせて、無理なく実践してみることが、継続のポイントとなります。必要に応じて、定期的に栄養士や医師に相談することで、さらに効果的な対策が見えてくるでしょう。
第7章:医療・行政・栄養のプロが伝える正しい豆知識
日々の食事や生活習慣の見直しで腸内環境を整えることが、花粉症やアレルギー症状の改善にどうつながるのか。ここでは、医療・行政・栄養といった各方面の専門家が長年の研究や臨床現場で得た知見をもとに、信頼できる豆知識をご紹介します。
1. 花粉症の根本的対策としての体内環境の整備
多くの医師が共通して指摘するのは、花粉症などのアレルギー症状は、単に外部の刺激に対する一過性の反応ではなく、免疫系と腸内環境との深い関連性が背景にあるということです。実際、厚生労働省や日本アレルギー学会の資料にも、免疫細胞の大半が腸に存在し、そこでの微生物との相互作用が免疫バランスの維持に欠かせないと解説されています。つまり、腸内における善玉菌の優勢な環境作りが、過剰なアレルギー反応を抑える鍵となるのです。
2. 行政や公的機関が提唱する健康情報
行政機関では、国民の健康維持のために食生活や運動習慣の改善を推奨しており、その一環として腸内環境の重要性が説かれています。日本の健康増進基本計画や食育の取り組みでは、発酵食品や繊維質を豊富に摂る食事の推奨がなされており、これが免疫の正常化につながるとされています。さらに、環境保健の視点からも、花粉症などの季節性疾患に対しては、生活習慣全体を見直す必要性が示されています。
3. 栄養学と最新の研究成果
栄養の専門家は、腸内細菌のバランスを整えるために、乳酸菌、ビフィズス菌、酪酸菌といったプロバイオティクスの摂取を強く推奨しています。これらの菌は、腸内で抗炎症作用を発揮し、免疫システムの誤作動を抑える役割を果たすと複数の研究で報告されています。最新の論文では、プロバイオティクスがアレルギー症状の改善に寄与する可能性について、具体的なデータとともにその効果が示されており、サプリメントや発酵食品の摂取が臨床でも評価されています。
4. 日常生活に役立つ豆知識
・規則正しい食事時間:毎食を決まった時間に摂ることで、腸の自律運動が活発になり、腸内の老廃物排出がスムーズになります。
・ストレス管理:精神的ストレスは腸内細菌のバランスを乱す大きな要因です。十分な睡眠とリラクゼーションを心掛けることで、体全体の免疫調整力が向上します。
・適度な運動:軽い有酸素運動は腸の血流を改善し、腸内環境に好影響を与えます。
・水分補給:日中にしっかりと水を摂取することで、腸内での食物繊維の働きが最適化され、便通の改善につながります。
5. 実践する上での留意点
専門家は、短期間で劇的な改善を求めるのではなく、長期的な取り組みが必要だと述べています。たとえば、1週間、1ヶ月と継続して同じ生活習慣を続けることで、腸内環境の変化が明らかになり、徐々にアレルギー症状の軽減が実感できるという報告があります。さらに、個々の体質に合わせた対策が重要であり、栄養士や医師と相談しながら進めることが望まれます。
これらの豆知識は、医療現場や公的機関、そして最新の栄養学研究の成果に裏付けられており、花粉症対策としての腸内環境改善の有効性を示しています。正しい知識をもとに、日常生活に少しずつ取り入れていくことが、健康的な春の過ごし方への第一歩となるでしょう。
第8章:まとめ 〜未来の花粉症対策への展望〜
ここまで、腸内細菌と花粉症の関係、そして腸内環境を整えるための具体的な対策について詳しく解説してきました。
改めてまとめると、花粉症は単なる一過性の症状ではなく、体内の免疫バランスと深く関係しており、その改善に腸内環境は大きな役割を果たしています。
1. 今後の対策の方向性
現在、腸内細菌叢の解析技術やプロバイオティクスの研究は急速に進んでおり、個々の体質に合わせたパーソナライズド腸活プランの提案も現実味を帯びています。今後は、定期的な腸内フローラ検査を通じて、自分に最適な食事やサプリメントを見つけることが、花粉症対策の新たなスタンダードになる可能性があります。
2. 実践の継続がもたらす健康効果
ここでご紹介した食事や生活習慣の改善は、花粉症対策だけでなく、全身の健康維持、免疫力向上、慢性疲労の解消など、多くの効果が期待できます。
このような積み重ねが、長期的には健康寿命の延伸や生活の質の向上にもつながるため、一度試してみる価値は十分にあると言えるでしょう。
3. 最後に
花粉症と腸内細菌という視点は、従来の花粉症対策とは一線を画す新しいアプローチです。医療・行政・栄養の専門家たちの知見に基づく正しい対策を日々の生活に取り入れることで、より健やかな春の日々を過ごすことができるでしょう。
現代の科学技術は、私たちに多様な健康情報を提供してくれます。これらの情報を活用し、自分自身のライフスタイルに合った方法で実践することが、未来の花粉症対策の鍵となります。
今回の記事の内容はいかがでしたでしょうか。
難しい内容ですが、腸内細菌ってすごいですよね。腸活って正しく行えば、ものすごく可能性を秘めた活動ですよね。言葉だけは知っていたけど、ここまですごいと思わなかった!という方も少なくないのでは。僕も調べていくうちに少しでも早く、たくさん腸内細菌に良い食事や行動をとらないと…と前向きな気持ちになりました。
や生活リズムなど、あらゆることを見直して、健康な身体を手に入れましょう!
さて、筋トレで身体を鍛えるだけでは強い身体にはなれません。
食事
もちろん筋トレも忘れずに!
暖かくなって外に出るのもワクワクするような気候になってきました。せっかくお出かけしたい気分なのに身体がうごかない・・・。とならないように、日々健康に気を遣い、マインドも前向きに保てるように、少しでも今回の記事が参考になれば幸いです。
筋トレが続かない、正しいやり方がわからない、と悩んでいる方は是非パーソナルトレーニングジムを訪れてください!