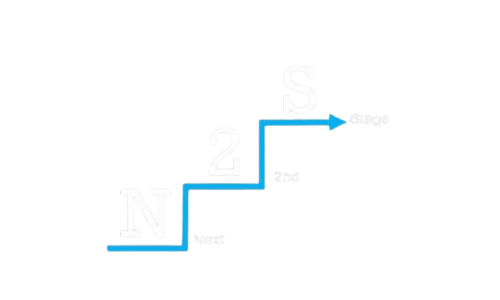NEWS
連休明けの体がだるい…5月の運動不足を解消するコツ
2025.5.5
はじめに:なぜ5月は体がだるいと感じるのか?
こんにちは!西宮門戸厄神駅前パーソナルトレーニングジム、N2Sパーソナルトレーナーの中阪です!
ゴールデンウィークが終わった5月のはじめ、「体が重い」「やる気が出ない」「疲れが抜けない」と感じていませんか?
実はこの時期、季節の変化・生活リズムの乱れ・運動不足などが重なり、心と体に負担がかかりやすくなるタイミングなんです。
新年度のスタートから1か月が経ち、緊張感がやや緩む一方で、急に気温が上がったり、気圧が不安定だったりと、知らず知らずのうちに体力やメンタルが削られているのです。
そこで今回の記事では、5月に感じやすい体の「だるさ」や「疲れ」を引き起こす原因と、それを解消するための【運動習慣】や【食事の工夫】について、パーソナルトレーナーの視点から丁寧に解説したいと思います。
普段多忙で新しいことに取り組むことが難しい方でも、「これならできそう!」と思えるヒントを多数紹介しますので、ぜひ日常に取り入れてみてください!
⸻
第1章:連休明けの「だるさ」の原因とは?
1-1. 生活リズムの乱れ
ゴールデンウィークは仕事や学校が休みになるため、夜更かしや寝坊、外出や旅行などで生活リズムが崩れやすい時期です。
今年2025年は最大11連休と、かなり長く休暇をとられた方もいるのではないでしょうか。長い休みはかなり嬉しいものですが、その後の社会復帰が大変ですよね(^^;)
翌日が休みだと、ついつい夜更かしして昼夜が逆転してしまうパターンもよくありますね。また、穏やかな過ごしやすい気候だとつい長めにお昼寝してしまって、夜に眠れないなんてことも・・・。
このような不規則な睡眠は体内時計のバランスを崩し、自律神経にも影響を与えます。
特に、自律神経は「オン」と「オフ」の切り替えを担当しているため、乱れたままだと日中でも眠気が抜けなかったり、集中力が続かないといった状態になります。
1-2. 運動量の低下による血行不良
連休中は外出が多くなる一方で、長時間の移動(車・飛行機・新幹線)や、食事会・映画鑑賞など「座る時間」が増える傾向があります。
これにより、下半身の筋肉が使われず血流が滞り、結果的に疲労物質が体に溜まりやすくなるのです。
血行不良が続くと、代謝の低下や冷え、むくみ、肩こりなどを引き起こし、「なんとなく不調」が長引く原因となります。
1-3. ストレスの反動
4月は新生活の始まりで、人間関係や仕事・学校の変化に伴うストレスが蓄積しやすい時期です。
連休で一旦は気が緩みますが、休み明けに再び日常へ戻る際に、その反動で自律神経が乱れ、「5月病」と呼ばれる無気力・疲労感の症状が現れる人も多くいます。
第2章:運動不足がもたらす影響
2-1. 筋肉量の低下と基礎代謝の減少
運動をしない日が続くと、真っ先に減っていくのが筋肉量です。特に下半身の筋肉は、日常の歩行や立ち座りで自然に使われている部分ですが、在宅ワークや移動の減少によって使われる頻度が極端に減ってしまいます。
筋肉が減ると基礎代謝も同時に下がり、以前と同じ食事量でも太りやすくなってしまう原因に。これは「太りやすい体質」への第一歩でもあり、健康的な体作りを目指すうえでは避けたい状態です。
2-2. 血流の悪化による冷え・むくみ
筋肉の収縮には“ポンプ機能”としての役割があり、全身の血液循環を促しています。運動不足になるとこのポンプ機能が働きづらくなり、血流が滞りやすくなります。
その結果、
次のような症状が現れやすくなります:
• 手足が冷える
• 足がむくむ
• 肩や首のこり
• 頭痛や倦怠感
これらは5月の「だるさ」の一因でもあり、放置していると慢性的な不調へとつながってしまいます。
2-3. 精神面への悪影響
運動はメンタルヘルスにも大きな影響を与えます。軽い運動をすることで、脳内に「セロトニン」「ドーパミン」といった“幸せホルモン”が分泌され、ストレスを軽減し、気分が明るくなる効果が期待されます。
しかし、運動不足が続くとこのホルモンの分泌量も減少。結果として、気分が落ち込んだり、不安感が増したりと、精神的にも不安定になりやすいのです。5月に多い「5月病」とも深く関係しており、運動不足と精神の不調は見過ごせないつながりがあります。
第3章:運動不足を解消するための簡単アクション
「運動不足を解消したいけど、何から始めればいいのかわからない」 「ジムに行くのはハードルが高いし、時間もない」 そんな人におすすめなのが、“日常に取り入れやすい小さなアクション”です。
ここでは、運動が苦手な方や忙しい方でも実践できる、簡単かつ効果的な方法を紹介します。
⸻
3-1. 1日10分のウォーキングから始めよう
運動不足の解消に最も手軽で効果的なのがウォーキングです。特に1日10分からでも、毎日の積み重ねが体に大きな変化をもたらします。
【ポイント】
• 通勤や買い物の際に一駅分歩く
• 昼休みに近くの公園を一周してみる
• 歩くときは“少し早歩き”を意識する ウォーキングは有酸素運動の一種で、脂肪燃焼効果や心肺機能の向上、気分転換にも役立ちます。
⸻
3-2. すきま時間の「ながら運動」
「忙しくて時間が取れない」という方には、“ながら運動”がおすすめ。
日常生活の合間にできるちょっとした運動を取り入れることで、知らず知らずのうちに活動量がアップします。
【例】
• 歯磨き中にかかと上げ運動
• テレビを見ながらスクワット5回
• エレベーターではなく階段を使う
• デスクワーク中の肩回し
・首回し
1つ1つは小さな動作でも、積み重ねることで血流促進や筋肉の活性化につながります。いかがでしょうか、今すぐにでも始められそうですよね!
⸻
3-3. 朝ストレッチで1日のスイッチを入れる
朝起きた後に軽いストレッチを行うことで、自律神経が整い、心身が目覚めやすくなります。
【おすすめストレッチ例】
• 深呼吸をしながら両手を天井にぐーっと伸ばす
• 前屈して太もも裏をゆっくり伸ばす
• 肩甲骨を意識して肩を大きく回す
ストレッチには副交感神経を刺激し、リラックス効果を高める働きもあるため、睡眠の質改善にもつながります。
ぜひ明日の朝からでも始めてみませんか?
⸻
3-4. “3日坊主”を防ぐコツとは?
やる気になって運動を始めても長く続かない…という方は多いもの。
継続することはとても大変です。続けるためには、以下のような工夫が効果的です。
• 目標は小さく設定する:「毎日10分だけ歩く」など
• スケジュールに組み込む:「朝食前にストレッチ」など
• 完璧を求めすぎない:「できない日があってもOK」と考える
• 可視化する:カレンダーにチェックを入れて達成感を得る 「頑張らないけど、やめない」ことが、長く続ける最大の秘訣です。
第4章:忙しくても続けられる運動の習慣化のコツ
5月は新年度の忙しさが続き、気づけば運動の時間を取れないまま1日が終わってしまう…という方も多い時期です。
しかし、ほんの少しの工夫で、無理なく運動を「習慣化」することができます。
ここでは、仕事・家事・学業で忙しい方でも実践しやすい、運動継続のコツを紹介します。
⸻
4-1. 習慣化の第一歩は「小さく始める」
最初から「毎日30分走る!」「筋トレ1時間!」と高い目標を立ててしまうと、途中で挫折しやすくなります。
ポイントは、小さく始めること。
【例】
• 毎朝ラジオ体操だけする
• 歯磨き中に5回スクワット
• 出勤時だけ階段を使う
「やろうと思えばすぐできる」くらいの小さなアクションを、まずは3日間だけ続けてみましょう。
頑張りすぎないこと、これがとっても大事なんです。
⸻
4-2. トリガーを決めて“ついで運動”を習慣化
トリガーとは英語で引き金のこと。「特定の行動とセットで運動をする」という方法は、習慣化にとても効果的です。
【例】
• コーヒーを入れる → スクワット10回
• 朝の洗顔後 → 肩回しストレッチ
• お風呂上がり → ヒップリフト30秒
「○○したら運動する」と決めることで、脳が自動的に動作を連動させやすくなり、忘れにくくなります。身体に覚えさせてしみ込ませましょう。
⸻
4-3. 運動を“ごほうび”に変える
継続のためには「楽しい」「気持ちいい」と感じることが大切です。
【おすすめのごほうび設定】
• 運動後に好きな音楽を聴く
• ストレッチ中に香りの良いアロマを焚く
• ウォーキング中にお気に入りのポッドキャストを聴く
• 習慣を1週間続けたら、自分にちょっとしたプレゼントを
“運動=嫌なこと”ではなく、“自分へのケアタイム”として脳にインプットしていくことが、長続きのカギです。
⸻
4-4. スマホやアプリでモチベーションUP
最近では、運動習慣をサポートする便利なアプリもたくさんあります。
【活用できるツール】
• 歩数計アプリ:目標歩数の達成をゲーム感覚で楽しめる
• 運動記録アプリ:日々の運動を「見える化」して継続に役立つ
• SNS投稿:今日やった運動を記録すると周囲の反応もモチベーションに
日々の積み重ねが“見える”だけで、「今日もやってみよう」という気持ちになれるはずです。
SNSでは同じ目的・目標を持った仲間と繋がることで、刺激になりモチベーションUPもできるでしょう。うまく活用してみましょう!
⸻
4-5. 続ける人が実践している「3つのキーワード」
運動を習慣にできた人たちが実践している“キーワード”をまとめてご紹介します。
小さく始める
1日5分でもOK。まずは「できた!」を積み重ねる。
習慣にする
毎日の生活に組み込んで「自動化」させる。
無理をしない できない日があっても自己嫌悪しない。
ゆるく続ける。
第5章:5月から始めたいおすすめの軽運動メニュー
「5月から運動を始めたい」「連休明けのだるさをどうにかしたい」
そんなあなたにぴったりの、体にやさしく、しかも効果のある軽めの運動を紹介します。
特に初心者でも取り組みやすく、自宅や外出先で手軽にできるメニューを厳選しました。
⸻
5-1. 朝のスイッチを入れる「おはようストレッチ」
朝起きてすぐに体をほぐすことで、自律神経が整い、1日をスムーズに始められます。
おすすめストレッチ3選(所要時間:約3分)
1. 背伸びストレッチ 両手を上に伸ばして深呼吸。血流促進&代謝アップに効果的。
2. 太もも裏伸ばし 座って前屈するだけ。下半身の血行が良くなり冷え・むくみ対策にも。
3. 肩甲骨回し 肩をぐるぐると大きく回す。首や肩のコリ、猫背対策におすすめ。
⸻
5-2. 通勤・買い物ついでにできる「ながらウォーキング」
移動を運動に変えるだけで、1日20〜30分の運動が自然に取り入れられます。
【ポイント】
• 一駅分歩く or 自転車で遠回りして帰宅
• 階段を使う(特に駅やショッピングモール)
• 歩くときは“かかとから着地して背筋を伸ばす” 【効果】
• 有酸素運動で脂肪燃焼
• 下半身の筋力アップ
• ストレス発散や気分転換
⸻
5-3. 室内でできる「簡単自重トレーニング」
自宅で静かにできるトレーニングで、筋肉を維持&基礎代謝アップを目指しましょう。
・スクワット足を肩幅に開いて腰を落とす。膝がつま先より出ないように(10回 × 2セット)
・ヒップリフト仰向け→膝を立ててお尻を上げる。お尻と太もも裏を意識(15回 × 2セット)
・プランク肘をついて体を一直線にキープ。腹筋と体幹に効果的(30秒 × 2セット)
無理せず、最初は週に2〜3回から始めましょう。キーワードは「頑張りすぎない」ことです!
5-4. おすすめ運動ルーティン(初心者向け)
【朝】ストレッチ3種・深呼吸(約3分)
【昼】早歩き or エレベーター→階段チャレンジ(約10分)
【夜】ヒップリフト&プランク(約5分)
合計たったの20分でOK!「少し体が動いた」「昨日よりも調子がいい」と感じられる日が増えていくはずです。
第6章:生活リズムを整えて“動きやすい体”を作る
5月は日中汗ばむ陽気で暑くても夜は肌寒いといった寒暖差や連休の影響で生活リズムが乱れやすく、体の不調を感じる人が増える時期です。
この章では、「だるさ」や「やる気の出なさ」を改善し、自然と運動したくなる体と心のコンディション作りについて解説します。
⸻
6-1. まずは「朝日」を浴びる
朝起きたら、まずはカーテンを開けて朝日を浴びることから始めましょう。
【朝日がもたらすメリット】
• 体内時計がリセットされ、生活リズムが整う
• 幸せホルモン“セロトニン”の分泌が促進される
• 自律神経が整い、日中の集中力や運動パフォーマンスも向上
ポイント:起床後30分以内に5〜10分ほど自然光を浴びるのが理想です。はじめてみると、とっても清々しく、今日も1日頑張ろう!と気分も上向くのでとてもお薦めですよ!
⸻
6-2. 食事でリズムを整える
「朝食を抜く」「夕食が遅い」「夜食を食べる」など、乱れた食習慣は代謝やホルモンバランスを崩す原因になります。
体が整う食事のタイミング
【朝食】起床後1時間以内炭水化物+たんぱく質で脳と体にスイッチON
【昼食】12:00〜13:00血糖値の急上昇を防ぐため、食物繊維を意識
【夕食】就寝の3時間前まで消化の良いメニューで睡眠の質を向上
6-3. 睡眠で疲れをリセット
睡眠は心と体の回復タイム。しっかり眠ることで運動効率も向上し、モチベーションも維持しやすくなります。
良質な睡眠を得るための3つの習慣
1. 寝る1時間前はスマホを見ない → ブルーライトが脳を覚醒させるためNG
2. 寝室は暗く・静かに → 遮光カーテンや耳栓、アロマもおすすめ
3. お風呂はぬるめのお湯で15分程度 → 深部体温が下がることで入眠しやすくなる
⸻
6-4. 自律神経を整える「リズム運動」もおすすめ
リズム運動とは、一定のリズムで繰り返す運動のこと。ウォーキングやゆっくりとした深呼吸、軽いジョギングなどが該当します。
【効果】• セロトニンの分泌が促進され、気分が安定• 自律神経が整い、体温・血圧・消化などの機能が正常化• 習慣化しやすく、続けるほどメンタルも安定
⸻
このように、体を動かしやすいコンディションは「生活リズム」によって整えられます。
運動を続ける土台づくりとして、日々の生活習慣を意識することもとても重要です。
第7章:おすすめの食べ物&栄養素で“疲れにくい体”に
5月のだるさを乗り越えるためには、「動くこと」だけでなく「食べること」も重要な鍵です。
食事からしっかりと栄養を補給することで、体の内側から元気が湧き、運動する意欲も高まります。ここでは、5月の疲れを和らげるための栄養素と、それらを多く含む食品を具体的に紹介します。
⸻
7-1. ビタミンB群:エネルギー代謝のサポート役
ビタミンB群は、食べたものをエネルギーに変えるために不可欠。
不足すると「疲れやすい」「集中力が続かない」といった不調が起こりやすくなります。
B1
働き:糖質の代謝、神経の働き含まれる食べ物:豚肉、玄米、納豆
B2
働き:脂質の代謝、皮膚や粘膜の健康含まれる食べ物:卵、レバー、牛乳
B6
働き:たんぱく質の代謝、免疫強化含まれる食べ物:鶏むね肉、バナナ、サツマイモ
【おすすめメニュー】・「豚肉とニラの炒め物」・「納豆と卵のごはん」など
7-2. ビタミンC:ストレス&免疫対策に
5月は新生活のストレスでビタミンCを多く消耗しがち。
また、気温の変化で風邪を引きやすい時期でもあるので、特にしっかり摂っておきたい栄養素です。
多く含む食品:
赤ピーマン、ブロッコリー、キウイ、イチゴ、柿
取り方のコツ:
・水溶性なのでスープや蒸し調理で効率よく摂取(ブロッコリーは茹でるとビタミンCが溶け出してしまうので、レンチンや蒸すことで無駄なく摂取しましょう。)
・一度に大量に摂るよりも、こまめに摂るのが効果的
⸻
7-3. 鉄分:倦怠感の原因を改善
「なんだかずっと疲れている…」という場合、鉄分不足による貧血の可能性もあります。
特に女性に多いです。
多く含む食品:レバー、赤身の肉、あさり、ほうれん草、小松菜
ポイント:
・ビタミンCと一緒に摂ることで吸収率アップ
・コーヒーやお茶は鉄の吸収を阻害するため、食後すぐは避ける
⸻
7-4. マグネシウム:神経と筋肉の安定に
疲れやすさ・こむら返り・イライラなどがある場合、マグネシウム不足も疑われます。
多く含む食品:アーモンド、豆腐、納豆、ひじき、玄米
おすすめ習慣:
・間食に素焼きナッツを取り入れる・ご飯を白米から玄米や雑穀米に変える
⸻
7-5. 乳酸菌&食物繊維:腸内環境を整える
疲れにくい体を作るには、腸内環境も大切。腸が整うと栄養吸収が良くなり、免疫力もアップします。
乳酸菌が多い食品:ヨーグルト、キムチ、ぬか漬け
食物繊維が多い食品:オートミール、ごぼう、海藻類、きのこ類
おすすめ組み合わせ:
・朝食にヨーグルト+バナナ+オートミール
・夕食にキムチときのこたっぷりの味噌汁
第8章:習慣化のコツ〜モチベーションを保つ3つの秘訣
運動を始めることは簡単でも、「続けること」は意外と難しいですよね。
特に5月は新年度の疲れが出てくる時期で、モチベーションが下がりやすくなります。
ここでは、誰でも実践できる「続けるためのコツ」を3つの視点からご紹介します。
⸻
8-1. 小さく始める:「1日1分」でもOK!
最初から完璧を目指さないことが、長く続けるコツです。
おすすめのスタート例:
• 階段を使うようにする• 歯みがき中にかかとの上げ下げ
• 寝る前に1分ストレッチ
「たった1分でも動いた」という成功体験が脳に“習慣の快感”を残します。
この積み重ねが自然と「もっとやりたい」気持ちにつながります。
⸻
8-2. 習慣化の仕組みを使う:「トリガー行動」を決める
何かの動作に紐づけて運動をすることで、継続しやすくなります。
朝、顔を洗った後ラジオ体操を1曲だけやる
コーヒーを入れた後スクワットを10回する
帰宅して着替えたら軽くストレッチをする
トリガーが明確だと、脳が“自動的に動く”モードに切り替わるため、意志の力に頼らずに続けやすくなります。
8-3. 成長を可視化する:「見える化」でやる気アップ
自分の頑張りを記録することで、達成感が得られ、次のやる気につながります。
おすすめの記録方法:
• カレンダーに〇印をつける
• LINEで自分にメモを送る
• アプリで歩数や運動時間を記録する(例:Google Fit、あすけん など)
さらに効果的なポイント:「体重が減った」「歩数が増えた」などの成果だけでなく、
「今日は疲れていたけどストレッチだけでもやった」など、“行動そのもの”を褒めることが大切です。
まとめ:モチベーションに頼らずに運動を「歯みがきレベルの習慣」にするには、
小さな行動の積み重ねと“見える化”がカギです。
「またサボってしまった…」と落ち込むよりも、「今日は1分でもやった自分、えらい!」と前向きに継続していきましょう!
第9章:パーソナルトレーニングで得られる3つのメリット
5月の運動不足を解消したいと感じていても、「何をすればいいか分からない」「続けられるか不安」という声も多く聞かれます。
そんな方にこそおすすめなのが パーソナルトレーニング。
プロのトレーナーと一緒に取り組むことで、自己流では得られない多くのメリットがあります。
⸻
9-1. 自分に合ったトレーニングメニューを提案してもらえる
人それぞれ、体力や目的は異なります。パーソナルトレーナーは、あなたの体力・生活習慣・目標に応じて、最適な運動プランを作成してくれます。
たとえば…
• 「デスクワーク中心で肩こりがひどい」→ 肩甲骨まわりを重点的に
• 「脚痩せしたい」→ 下半身中心のメニューに調整
• 「週に1回しか通えない」→ 家でできるメニューも併用
個別化されたあなただけのメニューで無理のないペースで進められるので、継続しやすくなります。
⸻
9-2. 正しいフォームでケガの予防&効果アップ
自己流トレーニングでは、フォームが崩れてしまいがち。
「これで合っているのか不安」「効いているか分からない…」初心者に限らずこのようなお悩みはつきものです。
間違った動きは、ケガのリスクや効果の出にくさにつながります。
パーソナルトレーナーが常に見守っていることで…
• 正しい姿勢で安全にトレーニングできる
• 鍛えたい部位にしっかり効かせられる
• 疲れやすい箇所を重点的にケアしてもらえる 結果として、最短距離で目標に近づけるのです。
⸻
9-3. モチベーションが維持できる環境がある
トレーニングを継続するうえで最も大切なのが「続ける環境」。
パーソナルトレーニングでは、トレーナーとのコミュニケーションや、予約制という仕組みがモチベーション維持に効果的です。
こんな効果があります:
• トレーナーの励ましで「やる気」がわく• 予約があると「今日は絶対行こう」と思える
• 成長を共有できる相手がいるから、頑張れる 「1人だとサボってしまう…」という方には特におすすめです。
⸻
パーソナルトレーニングジムに通うメリットまとめ
1. 個別メニュー体力や目標に合わせた専用プログラム
2. 正しいフォームケガ予防・効率アップ・目的に合わせた動きの習得
3. モチベーション維持コミュニケーション・予約制度・記録管理で習慣化を後押し
第10章:5月の運動習慣を成功させるためのまとめ
大型連休明けの5月は、気温の変化や生活リズムの乱れから体も心もだるくなりがちです。しかし、今ここで小さく一歩を踏み出すことで、運動不足を解消し、健やかな毎日への第一歩を踏み出せます。
この章では、これまでの内容を振り返りつつ、5月の運動習慣を成功させるための重要なポイントをまとめます。
⸻
10-1. だるさの正体を知り、焦らず向き合おう
5月に感じる「体のだるさ」の原因は、春の気温差や生活の変化、栄養の乱れ、ホルモンバランスの崩れなど様々です。
大切なのは、「だるいのは甘えじゃない」と受け入れて、自分に優しく、段階的に生活を整えることです。
⸻
10-2. 今すぐ始められる「小さな運動」が未来を変える
• 1分ストレッチ
• 軽い散歩
• 家事の合間にスクワット
こうした小さな動きでも、体は確実に変わっていきます。
「まずは1週間続けてみよう」「カレンダーに丸をつけてみよう」など、始めやすい工夫を取り入れましょう。
⸻
10-3. 食生活の見直しも運動とセットで
• 疲労回復にビタミンB群(豚肉、卵、納豆など)
• 抗ストレスにマグネシウム(ナッツ、バナナ)
• 腸内環境改善に乳酸菌や食物繊維(ヨーグルト、わかめ、玄米など)
コンビニでも手に入る食材でOK。体の中からリズムを整えることが大切です。
⸻
10-4. 習慣化のコツを活かして「続けられる」工夫を
• 小さく始める(完璧を目指さない)
• トリガー行動を決める(生活習慣に結びつける)
• 見える化で達成感を得る(記録をつける) 行動の「ハードルを下げる」ことで、日々の積み重ねが自然と自信に変わります。
⸻
10-5. パーソナルトレーニングという選択肢も
• 正しいフォームで効率よく安全に
• あなたに合ったプランで無理なく継続• トレーナーとのコミュニケーションがモチベーション維持に効果的 「1人では不安…」という方には心強いサポートとなります。
⸻ 最後に:5月は“リスタート”のベストタイミング!
5月は、「やり直し」ができる月です。
4月に立てた目標がうまくいかなかった人も、ここでもう一度、小さくスタートすれば十分。
今日から始めた「たった5分の習慣」が、1ヶ月後には見違えるような成果をもたらしてくれるかもしれません。
大切なのは、「できなかったこと」ではなく、「今日できた小さな一歩」です。
少しでも達成できたら自分を褒めてあげましょう!褒めるのと甘やかすの別物です!
⸻
今回の、5月に感じやすい体の「だるさ」や「疲れ」を引き起こす原因と、それを解消するための【運動習慣】や【食事の工夫】について、パーソナルトレーナーの視点から解説した記事はいかがでしたか?
ちょっとした工夫や意識で、毎年やってくる5月病をしっかり跳ね返していきましょう。
個人的に5月は1年で1番過ごしやすく大好きな時期です。
4月までは花粉でしんどい思いをしていて、6月からはじめじめした梅雨、7月から暑い夏が始まる、この貴重な過ごしやすいベストシーズンに、元気な身体でいろんな場所を訪れたりさまざまなことを体験したりしたいと思っています!
みさなんは5月にやりたいことはありますか?ゴールデンウィークが終わってしまっても、楽しい時間はまだまだ続きます!楽しく過ごすためには健康な身体とマインドがないと叶いません。
今日ご紹介した内容を活かして、あなたの5月が、健やかで前向きな月になりますように。
そのお手伝いをさせていただくのが僕の使命です!ぜひ筋トレや運動を始めようとしているかたは当ジムをお役立てください!
4月5月は新しい環境で新しいことにチャレンジする方が非常に多いです。パーソナルトレーニングのお問い合わせをかなり多くいただくのがこの時期。
始める時期は早いに越したことはありません。あなたのこれからの人生で今日が一番若い日ですからね!すこしでも健康で美しくカッコいい身体を長く維持しましょう。
筋肉はお金だけでは買えない財産です。あなたの努力とトレーナーのサポートで、より良い人生を手にしましょう!
少しでも気になってくださった方は、お気軽に公式LINEから無料トレーニング体験に申し込みください(*^^*)いつでもお待ちしております!