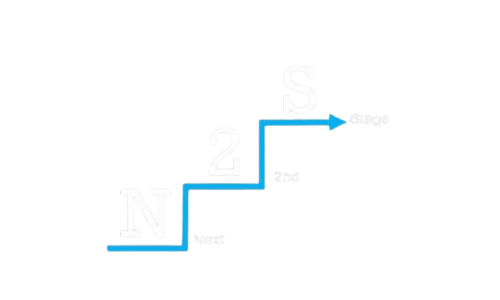NEWS
運動で整える5月の健康法
2025.5.11
こんにちは!西宮門戸厄神N2Sパーソナルトレーニングジム、トレーナーの中阪です!
第1章:5月病に悩まされているすべての方へ
春から初夏へと季節が移り変わる5月。新緑が美しく、過ごしやすい気候に感じられる一方で、「なんとなく体がだるい」「やる気が出ない」「頭が重い」といった不調を感じていませんか?
実はこの時期、気温の急激な変化や気圧の上下、生活環境の変化などが重なり、自律神経が乱れやすくなることが知られています。5月病という言葉もあるように、心身に不調をきたしやすいタイミングなのです。
さらに、ゴールデンウィークによる生活リズムの乱れや、仕事や学校での新しい人間関係によるストレスも加わり、疲れが抜けにくくなる人も少なくありません。
こうした不調を放っておくと、日常生活の質が低下するだけでなく、免疫力の低下や慢性的な体調不良につながるおそれもあります。
しかし、5月特有の体のだるさや気分の落ち込みは、日常に**「ちょっとした運動習慣」**を取り入れることで大きく改善できることをご存じでしょうか?
運動は、自律神経を整えるだけでなく、心と体のバランスを保ち、良質な睡眠や代謝の促進、そして免疫力の維持にも役立ちます。
本記事では、パーソナルトレーナーの視点から、5月の体調不良の原因をわかりやすく解説し、誰でも無理なく取り組める運動習慣やコンビニでも買える栄養補給法を紹介します。忙しい人でも実践できる方法ばかりですので、ぜひ最後までご覧くださいね。
第2章:季節の変わり目に起きる体調不良とは
季節の変わり目になると、「なぜか体調が悪い」「風邪でもないのにだるい」「気分が沈みがち」と感じる人が増えます。特に春から初夏に移り変わる5月は、朝晩の寒暖差や気圧の変化、生活環境の変化など、私たちの体にとって負担が大きいタイミングです。
こうした季節の変化が、なぜ不調を引き起こすのか。その鍵を握るのが「自律神経」です。
●自律神経とは?
自律神経は、私たちが意識しなくても呼吸・心拍・体温調節・消化などをコントロールしている神経で、「交感神経」と「副交感神経」の2つから成り立っています。
• 交感神経:日中の活動モード。心拍数を上げ、集中力を高める。
• 副交感神経:夜のリラックスモード。内臓の働きを整え、回復を促す。
この2つがバランスよく切り替わることで、私たちの心身は健康を保っています。しかし、寒暖差や気圧の変化が激しくなると、この切り替えがうまくいかなくなり、自律神経が乱れてしまうのです。
●代表的な不調の症状
5月に多い体調不良には、以下のようなものがあります:
• 慢性的なだるさ、疲労感
• 朝起きづらい、眠りが浅い
• 頭痛、肩こり、めまい
• 胃腸の不調(食欲不振・便秘・下痢など)
• 気分の落ち込み、集中力の低下
いかがでしょうか、あてはまる症状はありますか?
これらの症状は、一見すると風邪や病気のように思えますが、実際には「季節の変わり目による自律神経の乱れ」が原因であることも少なくありません。
●特に注意したい人の特徴
以下に該当する人は、季節の変わり目に不調を感じやすい傾向があります:
• 睡眠時間が不規則な人
• 日中の活動量が少ない人(デスクワーク中心など)
• 冷暖房の効いた室内に長時間いる人
• ストレスをため込みやすい人
• 運動習慣がない人
こうした状態が続くと、自律神経だけでなく、ホルモンバランスや免疫力も低下していき、さまざまな不調が慢性化する恐れがあります。
ですが、安心してください!
これらの不調は、運動を取り入れることで自然と整えていくことができます。
次章では、なぜ5月に不調を感じやすいのかを、さらに詳しく見ていきましょう。
第3章:なぜ5月は不調を感じやすいのか?
5月といえば、心地よい春の陽気とともにゴールデンウィークなどの連休もあり、リラックスできる時期と思われがちです。しかし、実際には「なんとなく不調」「やる気が出ない」と感じる人が増える季節でもあります。
この現象は、いわゆる「5月病」とも関連しており、心身のバランスを崩しやすくなる要因がいくつも重なっています。
ちなみに、5月病は、1960年代後半に大学新入生に症状がみられることが多く、1968年に流行語として使われ始めました。
当初は、大学の新入生がゴールデンウィーク明け頃に感じる虚脱感や無気力などを指す言葉として使われていましたが、現在では、新社会人や職場環境の変化など、様々な状況で起こる心身の不調を指す言葉として使われるようになったという歴史があるようです。
5月病は医学的な病ではありませんが、1960年代後半から生まれた概念なんですね。
1. 新生活によるストレスと疲労の蓄積
4月は新しい環境に身を置くことが多くなる季節です。進学、就職、異動などで人間関係や生活習慣がガラッと変わった人も多いでしょう。
最初の1か月間は緊張感で乗り切れていたとしても、5月に入るとその疲れがどっと出てくるのが特徴です。心と体に蓄積されたストレスが表面化し、「気持ちが沈む」「体が重い」といった症状を感じやすくなります。
2. 気温差・気圧変化による自律神経の乱れ
5月は日中と朝晩の気温差が10℃以上になることもあります。朝家を出るときは肌寒く、でも昼間は暑くなるから何を着て外出すればいいんだろうと悩んでしまうことも多いですよね。
体温調節を担う自律神経に大きな負荷がかかります。さらに、天気の変化によって気圧も不安定になり、頭痛やめまい、倦怠感といった不定愁訴を感じる人も増えます。
このような環境の変動に体がついていけず、疲れやすくなったり、眠りが浅くなったりするのです。
3. 連休明けの生活リズムの乱れ
ゴールデンウィークで生活が夜型になったり、運動習慣が途絶えてしまったりすると、自律神経のバランスはますます崩れやすくなります。特に、休み明けの出勤や登校は心身に強いストレスとなり、モチベーションの低下にもつながります。
4. 日照時間の変化とセロトニン不足
春は日照時間が長くなる季節ですが、天候によっては急に曇りや雨が続く日もあります。日光を浴びる機会が減ると、「幸せホルモン」とも呼ばれるセロトニンの分泌が低下し、気分が落ち込みやすくなります。
セロトニンは本ブログでも度々登場するホルモンですね。
これは運動によっても分泌されるため、運動不足のままでいると、メンタルの不安定さを感じやすくなるのです。セロトニンがたくさん分泌されている人は幸福度が高く、本当の意味での幸せ者でしょう。
⸻
このように、5月はさまざまな要因が複雑に絡み合い、不調を感じやすくなる時期です。次章では、これらの不調をどのように整えていけるのか、「自律神経」と「運動」の関係から探っていきましょう。
第4章:自律神経と気温差の関係
5月の不調を引き起こす大きな要因のひとつが、「気温差」による自律神経の乱れです。
では、なぜ気温の変化が体調に影響するのでしょうか?この章ではそのメカニズムと改善方法を解説します。
1. 自律神経とは何か?
自律神経は、私たちが意識しなくても体の機能を調整してくれている大切な神経です。例えば、心拍数、血圧、体温、消化機能、免疫などを24時間コントロールしています。
自律神経には以下の2つがあります:
• 交感神経(こうかんしんけい):主に昼間に活発になる「戦う・逃げる」の神経。体を活動モードにする。
• 副交感神経(ふくこうかんしんけい):主に夜間やリラックス時に働く。体を回復・修復モードにする。
この2つの神経がバランス良く働くことで、体と心は健康な状態を保つことができます。
2. 気温差が与える影響とは?
5月は日中が暖かく、朝晩はひんやりするなど、一日の中で寒暖差が10℃以上になる日も少なくありません。このような気温の変化が大きいと、体温調節をするために自律神経はフル回転します。
例えば:
• 朝晩の寒さに備えて血管を収縮させる
• 日中の暑さに対応するために汗をかいて体温を下げる
これらの調整を繰り返すことで、自律神経はオーバーワークになり、次第にバランスが乱れていくのです。
3. 自律神経が乱れると起こる症状
• 寝つきが悪くなる、夜中に目が覚める
• だるさ、疲労感が抜けない
• 食欲不振や便秘・下痢
• イライラ、不安感
• 集中力の低下
これらの症状は「なんとなく不調」として感じられるため、原因がわかりにくく見過ごされがちですが、自律神経の乱れが深く関係している場合が多いです。
4. 自律神経を整えるには?
自律神経を整えるためには、以下のような生活習慣の見直しが効果的です:
• 朝日を浴びて体内時計を整える
• 寝る前にスマホを見ない(ブルーライトを避ける)
• 温かいお風呂にゆっくり浸かる
• 深呼吸やストレッチを取り入れる
• リズムのある運動をする(ウォーキング、軽いジョギングなど)
特に「運動」は、自律神経を整えるうえで非常に有効です。
次章では、どんな運動が5月の不調に効果的なのかを詳しくご紹介します。
第5章:5月の不調に効く!おすすめの運動習慣
自律神経のバランスを整え、5月の不調を乗り越えるために有効なのが「運動」です。適度な運動は、血流を促進し、自律神経やホルモンバランスを正常に戻す助けになります。
この章では、誰でも無理なく始められる運動習慣とその効果をご紹介します。
1. 運動が自律神経に与える効果
• セロトニンの分泌促進
リズム運動(ウォーキングやジョギング、サイクリングなど)によって、幸せホルモンと呼ばれる「セロトニン」が分泌されやすくなります。セロトニンは、気分を安定させる神経伝達物質で、自律神経の調整にも関与しています。
• ストレスホルモンの減少
軽い運動でも、ストレスホルモン「コルチゾール」の分泌を抑えることがわかっています。緊張や不安を軽減し、リラックス効果が得られます。
• 睡眠の質の向上
適度な運動は睡眠の深さにも関係しています。夜ぐっすり眠れることで、副交感神経が優位になり、体の修復や回復が促進されます。
2. 5月におすすめの運動3選
(1)ウォーキング(1日20~30分)
春の気持ち良い陽気を感じながら、近所を歩くだけでも十分効果があります。おすすめは朝の時間帯。日光を浴びながら歩くことで、セロトニンの活性化が期待できます。
• ポイント:リズムよく、呼吸を意識しながら歩くこと。
• 効果:自律神経の安定、睡眠の質向上、血行促進。
(2)軽いストレッチ(朝・夜)
気温差によって体がこわばりやすい5月。朝や寝る前にストレッチを行うことで、筋肉の緊張がほぐれ、血流が改善されます。
• 朝は:交感神経をゆるやかに優位にするための“目覚めストレッチ”
• 夜は:副交感神経を優位にするための“リラックスストレッチ”
(3)スクワットや体幹トレーニング(週2~3回)
筋肉を刺激することで基礎代謝が上がり、体内の循環も活性化されます。特に下半身の筋肉は大きいため、代謝アップに効果的です。
• ポイント:無理をせず、自重で10回×2セットから。
• 効果:冷え改善、代謝促進、疲労回復。
3. 続けるコツと習慣化のヒント
目標は「気持ちいい」と思える範囲で
運動=つらいものというイメージを持つと長続きしません。「今日も少し歩けた」「昨日より肩が軽い気がする」など、小さな成功体験を積み重ねることが習慣化の第一歩です。
時間と場所を固定する
「朝起きてすぐストレッチ」「通勤前に駅までウォーキング」など、日常生活に自然と組み込めるタイミングを見つけましょう。
アプリや記録帳でモチベーションUP
スマホのヘルスアプリや、紙の運動日記で記録をつけると、自分の変化が目に見えてやる気が継続します。
第6章:睡眠の質もアップ!夜におすすめの軽い運動
なぜ“夜の軽い運動”が睡眠に良いのか?
5月は日照時間が伸び、活動量も自然と増えやすい季節です。しかし一方で、気温や湿度の変化、生活リズムの乱れによって「夜になっても寝つけない」「途中で目が覚める」といった睡眠の悩みを抱える人も少なくありません。
そんなときに役立つのが“夜に軽い運動”を取り入れる習慣です。激しい運動ではなく、ストレッチやヨガ、軽めのウォーキングといった運動が、自律神経を整え、心と体をリラックス状態へと導いてくれます。
睡眠に良いとされる軽い運動の例
1. 寝る1時間前の軽いストレッチ
• 特におすすめは肩・背中・股関節周辺の筋肉を伸ばすストレッチ。
• 血行が良くなり、体温が一時的に上がることで、その後の「体温の低下」とともに眠気がスムーズにやってきます。
2. ゆったりした呼吸に合わせたヨガポーズ
• 「チャイルドポーズ」や「仰向けのねじり」などが効果的。
• 腹式呼吸を意識しながら行うと副交感神経が優位になり、深い睡眠へ導いてくれます。
3. 夜の静かな道を10分歩く“リカバリーウォーク”
• 運動後すぐに寝るのではなく、帰宅後に入浴や水分補給をしてから睡眠準備に入るのがポイントです。
注意点とポイント
• 激しすぎる運動(筋トレやランニング)は交感神経を刺激し、逆に眠りにくくなることがあるので注意。
• 運動は就寝1~2時間前までに終わらせましょう。
• 運動後のスマホやPCのブルーライトも避けると、より睡眠の質が向上します。
更年期やPMSにも?女性が5月に感じやすい体調の揺らぎ
季節の変わり目と女性特有の不調の関係
5月は、新年度の慌ただしさが落ち着き始めた頃。一見、心身ともに安定しやすい時期と思われがちですが、実はこの時期に体調を崩す女性は少なくありません。
とくに注目すべきなのが、「更年期」や「PMS(月経前症候群)」の症状が季節の変わり目と重なることで、体調やメンタルの不安定さが強まる傾向にあることです。
その背景には、自律神経の乱れやホルモンバランスの変動、そして気温・気圧の変化による身体への負担が関わっています。
更年期・PMSの主な症状と5月の気候による影響
症状
詳細
5月に悪化しやすい理由
頭痛・肩こり
血流の悪化や自律神経の乱れからくる不調
気温差や新しい生活習慣へのストレスが引き金になる
不眠・寝つきの悪さ
エストロゲンの低下や精神的不安から生じやすい
気圧の変化で自律神経が乱れやすく、睡眠の質も低下
情緒不安定・イライラ
ホルモンバランスの乱れによる感情の揺れ
日照時間や生活の変化によってリズムが崩れることも
倦怠感・だるさ
血行不良やエネルギー代謝の低下
「5月病」の影響と重なりやすく、モチベーションが下がる
運動で整える!女性特有の不調との向き合い方
1. 軽めの有酸素運動で血行促進
ウォーキングや軽いジョギング、室内での足踏み運動など、“少し汗ばむ程度”の有酸素運動は、ホルモンバランスの安定やメンタルの安定に効果的です。
2. 骨盤周りのストレッチで下半身の冷え対策
PMS期や更年期に多い「冷え」は、血流と関節の可動域を改善することで軽減されます。骨盤まわりをほぐすストレッチやピラティスは特におすすめです。
3. 日光を浴びてセロトニン分泌を促す
朝の散歩や、昼休みの外出などで太陽の光を浴びることも大切です。セロトニンという「幸せホルモン」の分泌を促し、自律神経のバランスを整えてくれます。
⸻
食事との組み合わせでさらに効果アップ
• 鉄分・カルシウム・マグネシウムなど、ホルモン調整に役立つ栄養素を積極的に摂る
• 乳酸菌や発酵食品で腸内環境を整え、免疫力とメンタル安定の両方をサポート
• 甘い物やカフェインの過剰摂取は控えめに
⸻
5月は女性にとって“無理をしがちな月”でもあります。自分の体と心の声に耳を傾け、無理なく習慣化できる運動を取り入れることが、季節の揺らぎに強くなる第一歩です。
運動が続かない人に!モチベーションを保つ3つのコツ
「やる気が続かない…」は誰にでもある悩み
「健康のために運動しなきゃと思っているのに、続かない…」
「最初はやる気があったけど、三日坊主で終わってしまった…」
そう感じている方は多いのではないでしょうか?特に5月は、連休明けの疲れや気温の変化により“やる気”や“エネルギー”が下がりがちな季節でもあります。そこで大切なのは、「気合」や「根性」で続けようとするのではなく、「習慣化」できる工夫をすることです。
⸻
モチベーションを保つための3つの実践ポイント
1. 小さな目標から始める
いきなり「毎日30分走る」「週5でジムに行く」と決めてしまうと、達成できなかった時に落ち込みやすく、挫折の原因になります。
まずは「1日5分のストレッチ」「週に2回歩く」など、小さな成功体験を積み重ねることが大切です。
• 成功体験 → 自信 → 習慣化
• 例:「朝、歯磨きしながら足踏みする」「寝る前に3分ヨガ」
2. 達成を“見える化”して記録する
習慣を続けるコツは、自分の行動を「見える」形にすることです。アプリや手帳、カレンダーに「できた日」に丸をつけたり、コメントを書くだけでも効果があります。
• 継続が目で見えると達成感UP
• 自己肯定感も上がりやすい
おすすめアプリ例:
• あすけん(運動・食事管理)
• Habit Tracker
• Googleカレンダーとの連動で自動記録
3. “楽しい”を感じる工夫を取り入れる
「楽しい」と思える要素を加えることで、運動のハードルがぐっと下がります。
• 音楽をかけながらダンス感覚でストレッチ
• 推しの動画やドラマを観ながらエアロバイク
• 好きなウェアを着て“気分UP”
「やらなきゃ」より「やりたい」と思える環境づくりが、モチベーションを維持する最大のポイントです。
⸻
まとめ:続けるには“完璧を目指さない”こと
運動を習慣化するうえで、「できない日があっても大丈夫」という心の余裕もとても大切です。
大事なのは、「続けることそのもの」よりも「やめないこと」。
たとえ3日空いても、1週間空いても、また再開すれば“それも継続”なのです。
5月の体調リセットに、まずは小さな一歩から始めてみましょう。
第7章:季節の変わり目に摂りたい!体調を整える栄養素と食事の工夫
運動と並んで大切なのが「食事」。特に5月のような季節の変わり目には、栄養バランスの良い食事が、体調を整える大きなカギになります。
この章では、5月の不調に負けないために意識したい栄養素と、それを手軽に摂れる食材・食事法をご紹介します。
⸻
1. 不調対策に効果的な栄養素とは?
(1)ビタミンB群:疲労回復&エネルギー代謝を助ける
• ビタミンB1・B2・B6は、糖質や脂質の代謝に関与し、体内のエネルギー産生をサポートします。
• 【多く含まれる食材】豚肉、卵、納豆、玄米、バナナ、レバー
(2)ビタミンC:ストレス・免疫に強い体に
• ビタミンCは抗酸化作用が強く、ストレス対策や風邪予防に役立ちます。
• 【多く含まれる食材】ブロッコリー、パプリカ、キウイ、いちご
(3)鉄分・マグネシウム:だるさ・頭痛予防に
• 鉄不足は貧血や疲労感、集中力の低下につながります。マグネシウムは神経の興奮を抑え、睡眠の質を高める作用も。
• 【多く含まれる食材】あさり、ひじき、納豆、豆腐、アーモンド、ほうれん草
(4)トリプトファン:自律神経を整える“幸せホルモン”のもと
• セロトニンの材料となる必須アミノ酸。リズムよい運動とセットで摂ることで効果アップ。
• 【多く含まれる食材】豆腐、バナナ、乳製品、卵、鶏むね肉
⸻
2. 忙しい人でも取り入れやすい!簡単・時短の食事アイデア
コンビニで買える栄養バランス食の例:
時間帯
メニュー例
含まれる栄養素
朝食
納豆巻き+ゆで卵+バナナ
ビタミンB群、たんぱく質、トリプトファン、食物繊維
昼食
サラダチキン+雑穀おにぎり+野菜ジュース
たんぱく質、鉄分、ビタミン類
夕食
豆腐ハンバーグ+海藻サラダ+みそ汁
大豆たんぱく、マグネシウム、ミネラル
プチ工夫で栄養アップ!
• サラダに「ゆで卵」「ナッツ」「チーズ」などをトッピングする
• 飲み物を「野菜ジュース」「豆乳」「青汁」に変える
• コンビニの味噌汁やスープでミネラル・水分補給を忘れずに
⸻
3. 不足しがちな栄養素は“補助食品”も活用
どうしてもバランスよく食事を摂るのが難しい人は、サプリメントや栄養ドリンクを「補助」として取り入れるのも一つの手です。ただし、基本は“食事から摂る”ことを意識してください。
• 【ビタミンCサプリ】⇒忙しい朝や外出時に
• 【マグネシウムサプリ】⇒睡眠の質を高めたい人におすすめ
• 【プロテイン】⇒たんぱく質不足が気になるときに便利
第8章:5月の体調を守るために整えたい生活リズムとセルフケア習慣
春から初夏へと変わる5月は、心も体も“変化の波”に揺さぶられやすい時期。だからこそ、日常生活のちょっとした工夫が、体調管理の要になります。
この章では、誰でも今日から実践できる「生活習慣の整え方」と「セルフケアのヒント」をご紹介します。
⸻
1. 睡眠を最優先にする
なぜ5月は眠りが浅くなりやすい?
• 朝晩の寒暖差で自律神経が乱れる
• 新生活・新年度の疲れが蓄積してくる
• 日照時間の変化で体内時計がズレる
これらが重なると、眠りの質が低下し、翌日に疲れが残りやすくなります。
良質な睡眠のためのポイント:
時間帯
対策例
朝
日光を浴びて体内時計をリセット/軽く体を動かす
昼
仮眠するなら15~20分以内に/カフェインの摂取は午後3時まで
夜
入浴は寝る1~2時間前に/スマホは寝る30分前までにOFF/寝室を22~24℃に保つ
2. 食事と運動の「時間」も意識
• 食事の時間を毎日できるだけ一定に保つことで、体内時計(概日リズム)が安定します。
• 運動も“同じ時間帯にする”ことで習慣化しやすく、睡眠の質も向上します。
おすすめの運動時間帯:
• 朝の軽いウォーキング(セロトニンの分泌を促進)
• 夕方のストレッチ(副交感神経が優位になりやすい)
⸻
3. 呼吸と姿勢で“自律神経スイッチ”を整える
5月は「深呼吸」と「姿勢の見直し」が体調回復のキーポイントになります。
おすすめ:1日3分“呼吸リセット”
• 椅子に座って背筋を伸ばし、目を閉じる
• 4秒かけて鼻から息を吸う
• 6秒かけて口からゆっくり吐く
• これを3分間繰り返すだけ
副交感神経が優位になり、心身がリラックスします。
⸻
4. 心のケアも“生活リズム”から
春の終わりから5月にかけては、無自覚なストレスが溜まりやすい季節。「なんとなく不安」「やる気が出ない」などのメンタルの揺らぎも、生活リズムの乱れと深く関係しています。
実践したいメンタルケア習慣
• 朝日を浴びる習慣:セロトニン分泌が促進され、気分の安定に。
• 感謝日記を書く:1日1つ「今日よかったこと」を記録するだけでも、自己肯定感が上がるといわれています。
• スマホ時間を減らす:情報過多による疲労や不安感の軽減につながります。
⸻
5. 「整える習慣」は“無理なく、心地よく”
最も大切なのは、“がんばりすぎない”こと。
生活リズムを整える目的は「自分が気持ちよく過ごす」ためであり、完璧を目指す必要はありません。
• 眠れない日は、目を閉じて横になるだけでもOK。
• 食事が偏った日は、翌日に調整すればOK。
• 運動ができない日は、深呼吸だけでもOK。
「今日の自分にできることを一つやる」。この意識が、5月の不調を乗り越える原動力になります。
第9章:まとめ・5月の健康管理は“整える習慣”がカギ
5月は、春から初夏への季節の変わり目。ゴールデンウィーク明けの「だるさ」や「やる気が出ない」「体が重い」といった不調を感じやすい時期です。しかし、それは決してあなただけではありません。多くの人が体と心の“ゆらぎ”に直面する季節なのです。
だからこそ今、意識してほしいのは「整える」というキーワード。
⸻
1. 生活リズムを整える
• 起床・就寝の時間を安定させる
• 朝日を浴びて自律神経のリズムをリセット
• 1日3食+軽い運動で体のリズムをサポート
整った生活リズムは、自然と体調や気分を安定させる土台になります。
⸻
2. 食事で整える
• ビタミンB群、ビタミンC、鉄分、マグネシウムなど、不調に効果的な栄養素を意識
• コンビニでも買える組み合わせを工夫すれば、忙しくても栄養バランスは整えられます
• 食事の時間も一定に保ち、「食べること」自体をリズムに
⸻
3. 運動で整える
• ハードな運動でなくてOK。毎日のウォーキングやストレッチでも十分
• 呼吸法や軽い筋トレで、自律神経・筋肉・心を穏やかに整える
• 運動は“気持ちいい”が続くコツ。がんばりすぎず「できることから」で大丈夫
⸻
4. 心も整える
• ストレスを溜め込まないために、スマホ時間の見直しや“ありがとう日記”などを実践
• 完璧を求めず、自分をねぎらうことも忘れずに
• 小さな「できた」を積み重ねることが、自信と元気の源になります
⸻
5. 習慣の力は、思っている以上に強い
人の体と心は、「日々の積み重ね」でつくられています。
5月の不調をチャンスととらえ、“整える習慣”を少しずつ取り入れることで、
きっとあなたの生活は、季節とともに明るく軽やかに変化していきます。
⸻
最後に
パーソナルトレーニングジムでのサポートも、“整える習慣”の一つです。
一人では続けられない運動や健康管理も、専門家の力を借りればぐっと身近なものになります。
「最近なんだか不調…」
「何か始めてみたいけれど、何から手をつければいいか分からない」
そんなときこそ、ジムの扉をたたいてみてください。
あなたの「整える一歩」を、全力でサポートします!