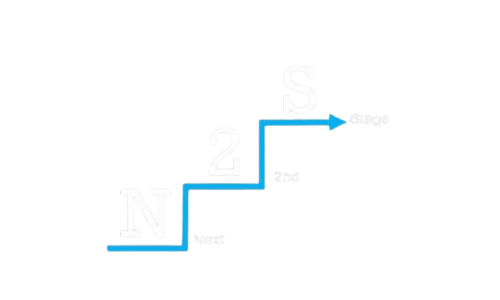NEWS
夏の疲れを引きずらない!“疲労回復メソッド”
2025.9.17
こんにちは!西宮門戸厄神駅前パーソナルトレーニングジム、N2Sパーソナルトレーナーの中阪です!
「夏の疲れがなかなか取れない…」
「お盆休みが明けても体がだるい…」
「気持ちは元気なのに、体がついてこない…」
そんな風に感じていませんか?
夏は強い日差しや高い気温、冷房、そして生活リズムの乱れによって、心も体も大きなダメージを受けています。その影響が「夏の疲れ(夏バテ)」として表れ、お盆明けや9月にかけて「疲労が回復しにくい」状態になりやすいのです。
ですが安心してください。
ちょっとした生活習慣を見直すだけで、夏の疲れは引きずらずにリセットできます!
この記事では、 専門的な知識をわかりやすく、パーソナルトレーナー風に解説しながら、夏の疲れを解消する具体的な方法 をご紹介します。
読めばすぐに実践できる内容ばかりなので、ぜひ日常に取り入れてみてください。
第1章:なぜ夏の疲れは長引くのか?その正体を知ろう
お盆明けから秋にかけて、「なんだか体がだるい」「やる気が出ない」「寝ても疲れが取れない」という声をよく耳にします。
実はこれ、ただの「夏バテ」や「年齢のせい」ではなく、体の中でいくつかの要因が重なっているからです。
1-1. 冷房による体温調整の乱れ
夏はどこへ行っても冷房が効いていますよね。オフィス・電車・スーパー・自宅…。
この「冷房の冷え」と「外の暑さ」を何度も行き来することで、自律神経が疲れてしまいます。
自律神経は体温や血流、内臓の働きをコントロールする司令塔。これが乱れると、
• 眠っても疲れが取れない
• 胃腸の調子が悪い
• 頭痛や肩こりが出る
などの不調が一気に現れます。
1-2. 暑さによる睡眠の質低下
夏は夜になっても気温が高く、寝苦しいことが多いですよね。
エアコンをつけっぱなしで体を冷やしたり、逆に暑くて何度も目が覚めたり…。
こうした「浅い睡眠」が続くと、疲労回復に欠かせない 成長ホルモン の分泌が減ります。
結果、筋肉や肌の回復も遅れ、「疲れやすい」「老けた気がする」という感覚につながるのです。
1-3. 夏の食生活の偏り
夏は冷たい飲み物やアイス、そうめんなど「喉ごしの良いもの」に偏りがちです。
すると、必要な栄養が足りず、体がエネルギーを作り出せない状態になります。
特に不足しやすいのが以下の栄養素です。
• ビタミンB群:糖質をエネルギーに変えるのに必要
• マグネシウム:疲労物質を分解するのに欠かせない
• タンパク質:筋肉やホルモンの材料
「食欲がないから」とサラダや麺類だけで済ませていると、ますます疲れが抜けなくなります。
⸻
第2章:疲労のタイプを見極めよう(あなたはどのタイプ?)
疲れといっても、人によって出方が違います。
ここでは代表的な3つの疲労タイプを紹介します。自分に当てはまるものをチェックしてみましょう。
2-1. 肉体疲労タイプ(体を使って疲れている人)
• 長時間の立ち仕事・移動が多い
• 筋肉痛や肩こりが続いている
• 「体が重い」と感じる
👉 このタイプは、筋肉中にたまった 乳酸 や、エネルギー不足が原因。
栄養補給と軽めのストレッチが効果的です。
2-2. 精神疲労タイプ(ストレスで疲れている人)
• 眠っても頭がスッキリしない
• イライラや不安感が強い
• デスクワークで目や脳を酷使している
👉 このタイプは、自律神経の乱れや脳の酷使が関係しています。
リラックスできる環境作り、深呼吸やヨガなどがおすすめ。
2-3. 内臓疲労タイプ(食生活や飲み過ぎが原因)
• 胃もたれ・便秘・下痢を繰り返す
• 暴飲暴食をしてしまった
• 甘いものやお酒をよく摂る
👉 内臓疲労は「腸内環境の乱れ」がポイント。
消化にやさしい食事や、発酵食品で腸を整えることが必要です。
2-4. チェックリストで確認!
以下のチェックをして、当てはまる数が多いタイプがあなたの傾向です。
• 朝起きても疲れが抜けない
• 手足が冷える
• 胃腸の不快感が続いている
• 気分が落ち込みやすい
• 集中力が続かない
⸻
第3章:食事から整える“疲労回復メソッド”
疲労回復のカギは「何を食べるか」です。夏の疲れを引きずらないためには、栄養バランスの見直しが必須。
3-1. 疲労回復に欠かせない栄養素
• ビタミンB群(豚肉、納豆、卵)
→ 糖質をエネルギーに変換。夏バテの食欲不振にも効果。
• クエン酸(レモン、梅干し、酢)
→ 乳酸を分解し、疲れを早く取り除く。
• 鉄分(赤身肉、ひじき、ほうれん草)
→ 酸素を体中に届ける。貧血気味の人に特に必要。
• タンパク質(鶏むね肉、魚、大豆製品)
→ 筋肉・ホルモンの材料となり、代謝を支える。
• オメガ3脂肪酸(サバ、アジ、亜麻仁油)
→ 炎症を抑えて疲労の蓄積を防ぐ。
3-2. 夏におすすめの疲労回復レシピ例
• 豚しゃぶの梅おろし和え
→ ビタミンB1+クエン酸で疲労物質を分解。
• 冷やし納豆そば+温泉卵
→ 食欲がない時も食べやすく、タンパク質も補給できる。
• サバ缶とトマトの冷製パスタ
→ オメガ3脂肪酸+リコピンで抗酸化&疲労回復。
• 豆腐とわかめの味噌汁
→ 消化にやさしく、腸内環境を整える。
3-3. 避けたいNG食習慣
• アイス・清涼飲料水のとりすぎ(内臓を冷やす)
• 夜遅くの暴飲暴食(消化に負担)
• カフェインの過剰摂取(自律神経を乱す)
第4章:食事で整える ― 夏疲れリカバリー栄養学
夏の疲労を回復させるためには、まず 「栄養をどう摂るか」 が大きなカギを握ります。食欲が落ちて「そうめんや冷たい飲み物ばかり…」という生活を続けていると、エネルギー代謝に必要な栄養素が不足し、疲れが取れないまま秋に突入してしまいます。
ここでは、疲労回復のために積極的に摂りたい栄養素と、具体的な食材・レシピのアイデアをご紹介します。
⸻
1. ビタミンB群 ― エネルギーを作り出す栄養素
糖質や脂質を効率よくエネルギーに変えるのに欠かせないのが ビタミンB群。特に「疲れに効くビタミン」と呼ばれるB1は、夏の疲労回復に必須です。
• ビタミンB1:豚肉、うなぎ、玄米、大豆
• ビタミンB2:レバー、卵、アーモンド
• ナイアシン(B3):まぐろ、かつお、鶏胸肉
👉 例:豚しゃぶ+玄米+冷ややっこ
冷しゃぶなら夏でも食べやすく、ビタミンB1とタンパク質を同時に補給できます。
⸻
2. ミネラル ― 汗で失われる大事な要素
夏は汗と一緒に カリウム・マグネシウム・亜鉛 などが流れ出ます。これらは神経や筋肉の働きに不可欠で、不足すると「だるい」「足がつる」「イライラする」といった症状が出ます。
• カリウム:バナナ、ほうれん草、きゅうり、すいか
• マグネシウム:海藻類、ナッツ類、豆腐
• 亜鉛:牡蠣、牛肉、カシューナッツ
👉 例:豆腐とわかめの味噌汁+すいか
シンプルですが、失ったミネラルを効率よくチャージできます。
⸻
3. 抗酸化ビタミン ― 紫外線ストレスから細胞を守る
夏に強い紫外線を浴びると、体内では活性酸素が増加。これを中和するのが ビタミンC・ビタミンE・βカロテン です。
• ビタミンC:パプリカ、キウイ、ブロッコリー
• ビタミンE:アーモンド、アボカド、かぼちゃ
• βカロテン:にんじん、かぼちゃ、トマト
👉 例:アボカドとトマトのサラダ+レモン風味ドレッシング
⸻
4. 胃腸をいたわる「温×消化の良い食材」
冷たいものを摂りすぎて弱った胃腸には、温かいスープや消化に優しい食材を。
• おかゆ、うどん、温野菜スープ
• ショウガ・ねぎ・しそで血流アップ
⸻
💡 まとめ
夏疲れ回復の食事は、
「ビタミンB群+ミネラル+抗酸化ビタミン+温かい食材」 の黄金バランスがポイントです。
⸻
第5章:睡眠でリカバリー ― 深い休息を取り戻す方法
夏の疲労をリセットするうえで「睡眠の質」は欠かせません。特に日本の夏は寝苦しさや冷房の使い方で眠りが浅くなりがちです。ここでは、疲労回復に直結する「ぐっすり眠るためのポイント」を解説します。
⸻
1. 寝る前のルーティンを整える
• ぬるめの入浴(38〜40℃で15分)
血流が改善し、自律神経が副交感神経優位に切り替わりやすくなります。
• スマホを30分前にオフ
ブルーライトがメラトニン分泌を妨げ、寝付きが悪くなります。
⸻
2. 室温・湿度を最適化する
• 室温:26〜28℃
• 湿度:50〜60%
冷房をタイマーで切ってしまうと寝苦しさで途中覚醒するので、弱冷房+除湿で一晩中つけっぱなしがおすすめです。
⸻
3. 食事・飲み物の工夫
• 寝酒はNG:眠りが浅くなる
• カフェインは夕方以降避ける:コーヒー・緑茶・チョコも注意
• 温かいハーブティー(カモミール・ルイボスなど)はリラックス効果大
⸻
4. 「睡眠ホルモン」を作る栄養素
• トリプトファン(バナナ・大豆・牛乳):メラトニンの材料
• マグネシウム(ナッツ・海藻):神経をリラックスさせる
• GABA(発酵食品):ストレス軽減
👉 夜に「バナナ+ホットミルク」は王道の快眠コンビです。
⸻
💡 まとめ
睡眠の質を高めるには、
「環境調整+ルーティン+栄養」 の3本柱を意識しましょう。
⸻
第6章:運動で血流改善 ― 疲労物質をためない体に
運動というと「疲れているのに動いて大丈夫?」と思う方も多いですが、実は 適度な運動こそが疲労回復の近道 です。
⸻
1. 運動が疲労回復に効く理由
• 血流促進:乳酸などの疲労物質を排出しやすくなる
• 自律神経調整:リズミカルな運動で交感神経と副交感神経の切り替えがスムーズに
• ホルモン分泌:運動で分泌される「セロトニン」「エンドルフィン」が心身を回復させる
⸻
2. 夏疲れリカバリーにおすすめの運動
• ウォーキング(20〜30分)
リズム運動でセロトニンUP。朝の光を浴びるとさらに効果的。
• ヨガ・ストレッチ
固まった筋肉をほぐし、副交感神経を優位に。
• 軽めの筋トレ
スクワット・プランクなど自重でOK。筋肉を動かすことで基礎代謝を維持。
⸻
3. 運動のタイミング
• 朝のウォーキング:体内時計リセット+自律神経が整う
• 夜のストレッチ:深い眠りにつながる
⸻
4. 注意点
• 激しい運動は逆効果。息が上がりすぎないレベルを目安に。
• 水分補給はこまめに。スポーツドリンクよりも「水+塩分補給」の方が低カロリーで◎。
⸻
💡 まとめ
疲労回復を目指すなら、
「有酸素運動+ストレッチ+軽い筋トレ」 のバランスが最強です。
第7章:温活習慣で基礎代謝を高める
夏の疲れが抜けにくい人の多くは、体が冷えて代謝が落ちていることが多いです。冷房や冷たい飲み物の影響で「内臓冷え」になり、エネルギーの巡りが悪くなっています。ここでは「温活習慣」を取り入れて、基礎代謝を底上げする方法を解説します。
⸻
1. 温活の基本 ― 「体を温める3つの柱」
• 食事で温める:ショウガ、にんにく、唐辛子、根菜類
• 運動で温める:下半身の筋肉(太もも・お尻)を動かすと血流改善
• 生活で温める:腹巻き・湯たんぽ・お風呂
👉 特に「首・手首・足首」の3つの“首”を温めると効率的に全身が温まります。
⸻
2. 夏こそ「お風呂習慣」が疲労回復の近道
• ぬるめ(38〜40℃)で15分の半身浴
• 入浴剤に「エプソムソルト」や「炭酸ガス」を加えると疲労物質の排出が促進
• 入浴後は白湯をコップ1杯飲むと血流がさらに改善
⸻
3. 温活ダイエットの相乗効果
• 代謝が高まり、脂肪燃焼効率がUP
• 内臓機能が改善して便秘・むくみ解消
• 自律神経が整い、睡眠の質も改善
💡 まとめ
「温活=体を温める習慣」を継続すると、疲労回復とダイエットの両方に効果的です。
⸻
第8章:生活習慣をリセット ― 3日間集中リカバリープラン
お盆明けや長期休暇の後は「生活リズムが乱れている状態」。そこで、まずは 3日間集中でリズムを整える プランを実践するのが効果的です。
⸻
1日目:リズムを戻す「デトックスデー」
• 朝:白湯+軽めのストレッチ
• 食事:野菜スープや玄米おかゆで消化を助ける
• 夜:ぬるめの入浴+早めの就寝
👉 ポイントは「胃腸を休める」こと。冷たいものは避け、温かい消化の良い食事を。
⸻
2日目:血流を改善する「巡りデー」
• 朝:軽いウォーキング+日光浴
• 食事:タンパク質(鶏胸肉や豆腐)+発酵食品
• 夜:ヨガやストレッチでリラックス
👉 ポイントは「血流と腸内環境の改善」。
⸻
3日目:深い睡眠を取り戻す「リカバリーデー」
• 朝:起床後すぐカーテンを開けて朝日を浴びる
• 昼:リズミカルな運動(20分のウォーキング)
• 夜:就寝前のデジタルデトックス
👉 ポイントは「体内時計をリセット」すること。
⸻
💡 まとめ
たった3日間でも、食事・運動・睡眠の黄金バランス を意識すると、夏疲れが一気に軽減します。
⸻
第9章:よくある質問(Q&A)で疑問解消
疲労回復や温活ダイエットについて、よくある質問をまとめました。
⸻
Q1. 汗をかかないと疲労回復にならない?
👉 汗をかくこと自体が目的ではなく、「血流改善」が大切。ウォーキングや入浴でも十分に効果があります。
Q2. 夏に温かい食事はしんどいのですが…
👉 冷たいものを常に摂る方が胃腸の負担が大きいです。常温の水や、常温に近いお茶から始めるのがおすすめ。
Q3. 更年期世代でも疲労回復・ダイエット効果はある?
👉 もちろん可能です。基礎代謝が落ちている分、「温活+軽い筋トレ」が特に効果的です。
Q4. 運動初心者でも大丈夫?
👉 全く問題ありません。むしろ「軽めの運動」から始める方が疲労回復には向いています。
⸻
第10章:ジム活用で「続く習慣」を作る
自宅でできる温活・運動・食事法も効果的ですが、 一番の課題は「続けること」 です。ここで活用したいのが パーソナルトレーニングジム。
⸻
1. マンツーマンサポートで習慣化
• その人に合った運動強度・フォームを指導
• 疲労が強い時は「回復系ストレッチ」に切り替え可能
• 定期的に通うことで「リズムを整える仕組み」になる
⸻
2. 栄養・生活指導も同時に受けられる
• 食事の記録を見ながら改善ポイントをアドバイス
• 睡眠・ストレス対策まで含めたトータルサポート
⸻
3. 実際に通った方の声(イメージ例)
• 「冷え性が改善して朝から元気に動けるようになった」
• 「運動初心者でも続けられて、夏バテしなくなった」
• 「更年期の不調が楽になり、ダイエットも成功した」
⸻
💡 まとめ
疲労回復メソッドを本当に続けるには、 「仕組み化」=ジム活用 が最短ルートです。
N2Sパーソナルトレーニングジムでは「完全個室・子連れOK・マンツーマンサポート」で、あなたに合った疲労回復&ダイエットプランをご提案します。